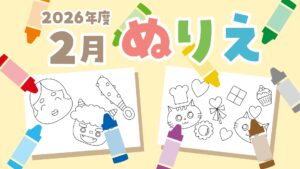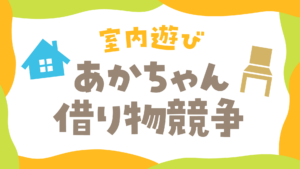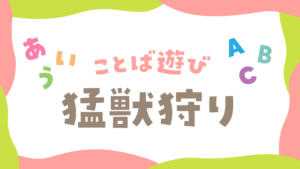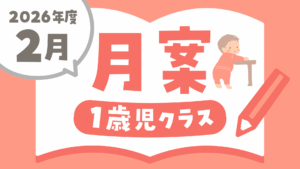11月23日は「勤労感謝の日」。
保育の現場でも「はたらくってなあに?」「ありがとうを伝えるってどういうこと?」といった問いに子どもたちと向き合う大切な行事です。
今回は「勤労感謝の日とはどんな日なのか」「どんな意味や由来があるのか」をわかりやすく解説し、子どもたちへの伝え方や保育活動のアイデアもご紹介します。
家庭や園で“感謝の気持ち”を育むヒントにご活用ください。
勤労感謝の日とは
勤労感謝の日は、1948年(昭和23年)に「国民の祝日に関する法律」により定められた祝日で、毎年11月23日に行われます。
法律上の趣旨は「勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう日」。働くことの尊さや、働く人たちへの感謝の気持ちを国全体で共有することを目的としています。
現在では、家庭・保育・学校などで、子どもたちが「働く人=誰かのために何かをしている人」を身近に感じる機会として、大切にされています。
勤労感謝の日の由来
勤労感謝の日の由来は、古代の日本で行われていた「新嘗祭(にいなめさい)」という収穫祭にさかのぼります。
新嘗祭は天皇がその年の収穫に感謝し、神様に新米を供える伝統行事で、古くは飛鳥時代から続いていたとされます。
昭和23年の祝日法制定時に「新嘗祭」は名称を変えて「勤労感謝の日」となりました。
つまり、「勤労感謝の日」は、もともと自然の恵みと農作業への感謝を表す日だったのです。

子どもへのわかりやすい説明
2歳児への説明
2歳児には
「ありがとうを言う日だよ」
と優しく伝えましょう。
「いつもごはんをつくってくれる人」「あそんでくれる先生」にありがとうを言う体験が大切です。
「きょうはありがとうって たくさん言ってみようね」
と語りかけ、感謝の気持ちを言葉にする第一歩にします。
由来や“働く”の説明は避け、身近な人とのやりとりを大切にしましょう。
3歳児への説明
3歳児には
「はたらく人ってどんな人かな?」
と問いかけながら話を始めましょう。
「お店の人」「先生」「おうちの人」などを一緒に思い浮かべ、
「みんなが しあわせに すごせるように がんばってくれてるんだよ」
と伝えると、理解が深まります。
由来は
「むかしの人たちは、おこめがたくさんとれたことをよろこんで“ありがとう”って言ってたんだって」
と、簡単な言葉で伝えましょう。
4歳児への説明
4歳児には、
「働くっていうのは、みんなのために何かをすることなんだよ」
と少し具体的に伝えることができます。
「例えばお父さんやお母さんはお仕事をして、家族がおうちでごはんを食べられるようにしてくれるね」
「先生はみんなが楽しくすごせるように働いてるんだよ」
「そんなはたらいている人達へ、ありがとうっていう日なんだよ」
など、日常に即した説明が効果的です。
由来については、
「むかしは、たくさんお米がとれたら、かみさまにありがとうって言ってお祝いをしたんだよ」
と、自然と人との関係を伝えていきましょう。
5歳児への説明
5歳児には
「勤労感謝の日は“はたらく人にありがとう”を伝える日なんだよ」
と伝え、身近な人たちに感謝する対象を広げて考えられるようにします。
「はたらくっていうのは、みんなが生きるために たいせつなことをしてるんだよ」
と、子ども自身が“はたらく”ということを少しずつ理解するきっかけになります。
由来については、
「むかしは食べものを育ててくれた自然や人に“ありがとう”っておまつりをしていたんだよ」
と、文化のつながりも含めて伝えるとよいでしょう。

関連情報
勤労感謝の日は、ただ“感謝を伝える日”ではなく、
「働くことってどういうこと?」
を子どもなりに考える入口にもなります。
保育現場では、保育者自身の働き方や、園の中での“みんなの役割”を可視化する工夫も効果的です。
また、家庭とも連携し、「おうちの人に“ありがとうカード”を渡す」「保護者のお仕事インタビューを共有する」など、園と家庭の架け橋としての活用もおすすめです。
子どもたちが“はたらく”ことをポジティブに感じられるように伝えていきましょう。
勤労感謝の日にちなんだ保育活動
- ありがとうカード作り:おうちの人や先生、給食室の人へ感謝のメッセージを絵や言葉で表現。
- おしごとごっこあそび:パン屋さん・郵便屋さん・お医者さんなど、働く人になりきって遊ぶ体験活動。
- “ありがとうの会”の開催:子どもたちが手作りのカードや歌で、園内の職員に感謝を伝えるセレモニー。
- 地域のお仕事を知る活動:消防署・郵便局などに見学やお礼のお手紙を送る(またはオンライン紹介)。
子どもたちが“感謝を形にする”経験を通して、「ありがとう」の重みや喜びを感じられるようにしましょう。
まとめ
勤労感謝の日は、子どもたちにとって「働く人を知る」「ありがとうを伝える」きっかけとなる行事です。
保育現場では、年齢に応じた伝え方や遊びを通して、“感謝の気持ち”を自然に育むことができます。
また、家庭や地域との連携を通して、行事が一過性のイベントではなく、「心に残る体験」となるように工夫することが大切です。
今年の勤労感謝の日は、子どもたちと一緒に、ありがとうの気持ちを広げてみませんか?