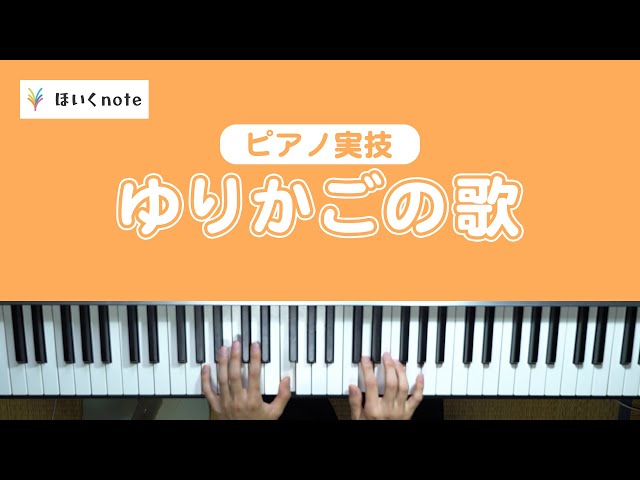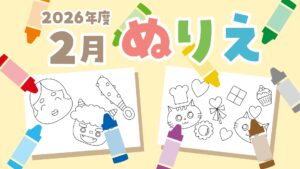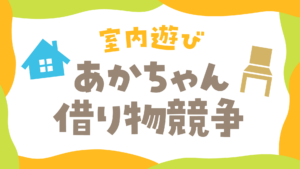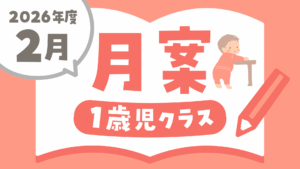夏になると、どこか懐かしい雰囲気を感じる風習「お盆」があります。
日本に古くから伝わるこの行事は、ご先祖さまを迎えて供養する大切な時間です。
保育の現場でも、子どもたちに日本の文化や命のつながりをやさしく伝えるきっかけとして活用できます。
今回は「お盆とは何か」「どうして行われるのか」など、幼児にもわかりやすく説明できるよう、保育に活かせる情報を分かりやすくご紹介します。
「お盆」とは
お盆(正式には「盂蘭盆会〈うらぼんえ〉」)は、亡くなったご先祖さまの霊をお迎えして供養する、日本の伝統行事です。
毎年8月13日から16日にかけて行われることが多く、地方によっては7月に行う地域もあります。
期間中は家族でお墓参りに行ったり、家の前で迎え火・送り火を焚いたりします。
地域によっては盆踊りや灯籠流しなどの行事も行われ、夏の風物詩のひとつとして親しまれています。
お盆は「命をつなぐ文化」として、次の世代へと伝えていくべき大切な行事ですね。
お盆の由来
お盆の起源は仏教の「盂蘭盆経(うらぼんきょう)」という経典にあります。
釈迦の弟子・目連(もくれん)が、亡き母が地獄で苦しんでいる姿を知り、お釈迦さまの教えに従って供養したところ、母が救われたという故事に由来しています。
これが「ご先祖の霊を迎え、供養する」というお盆の考え方のもととなりました。
また、日本では仏教の教えと古来からの祖霊信仰が融合し、現在のような形に発展しました。地域や宗派によって行事の内容に違いがあるため、諸説あることを理解しておくとよいでしょう。

子どもへのわかりやすい説明
2歳児への説明
2歳児には「お盆」という言葉そのものが難しいため、まずは
「おじいちゃんのおじいちゃんや おばあちゃんのおばあちゃんたちが にこにこして かえってくる ひなんだよ」と優しく語りましょう。
迎え火やお墓参りの絵本などを使い、「おうちで こんにちはって するんだって」といった身近な表現で伝えると、安心して受け入れやすくなります。
由来については触れず、「おじいちゃん おばあちゃんに おはなを あげようね」と、供養の行為を体験として伝えることが効果的です。
3歳児への説明
3歳児には
「おぼんは、おじいちゃんのおじいちゃんや おばあちゃんのおばあちゃんたちの たましいが いえに かえってくる じかんだよ」と少し具体的に伝えられます。
「かみさまみたいに、みえないけど だいじなひとが くるんだよ」と表現すると、目に見えない存在に興味を持てます。迎え火・送り火や仏壇などのイメージを実物の写真やイラストで見せながら話すと理解が深まります。
由来については、「むかし、あるひとが たいせつな おかあさんのために、おいしいごはんを つくって あげたんだって」と、物語としてかみくだいて話すのがよいでしょう。
4歳児への説明
4歳児には、お盆の行事全体を「たいせつなひとを おもいだして、ありがとうを つたえるひ」として伝えます。
たとえば「おじいちゃん おばあちゃんが おそらから かえってきて、おへやに すわってるかもね」と伝えると、イメージが広がります。
由来については「むかし、あるおしょうさんが じぶんのおかあさんのために、いのりをしたら おかあさんをたすけられたんだって。それをみんなが まねするようになったんだよ」
と、因果関係がわかるような話にすると理解しやすくなります。
5歳児への説明
5歳児には、お盆の意味と由来をより深く伝えることができます。
「おぼんっていうのは、もうあえない たいせつな ひとに、また こころで あう ことができる ひなんだよ」と語り、「どうしてそんな日があるのか」を子ども自身が考えるきっかけにもなります。
由来の説明では
「むかし、あるひとが おかあさんが つらそうにしているのをしって、どうしたら たすけられるかを かんがえて、たくさんのひとを たすけたんだよ。だから、みんなで ありがとうって するようになったんだね」
と、道徳的な要素も含めて伝えると、深い理解につながります。

お盆に関連する情報
お盆の行事は、保育の中で「いのち」「かぞく」「つながり」について子どもたちと考えるよい機会です。
お墓参りや灯籠流しなど、直接的な体験が難しい場合でも、絵本の読み聞かせや、盆踊りの音楽に合わせたリズム遊び、精霊馬(しょうりょううま)づくりなど、子どもたちの発達段階に応じた活動が可能です。
また、お盆の文化は地域差も大きいため、子どもたちの家庭での過ごし方を聞いてみると、それぞれの文化を尊重する多様性の学びにもつながります。行事の背景を大人がしっかり理解しておくことが、保育の質を高めるポイントです。
お盆にちなんだ保育活動
子どもたちが「伝統」を「たのしいもの」として感じられるような活動を取り入れると、自然と文化への関心が育まれます。
⚫︎盆踊りあそび:地域の民謡やわらべうたに合わせて簡単な振付を取り入れ、伝統行事の雰囲気を味わうことが出来ます。
⚫︎精霊馬づくり:なすやきゅうりの代わりに紙粘土やクラフト素材を使って動物の形を作ることで、伝統を工作として体験することが出来ます。
⚫︎「ありがとう」を伝える絵本づくり:家族のことを思いながら、好きな人に向けて感謝の気持ちを描いた絵本やカードを作成してみるのもいいですね。
⚫︎夏の思い出トークタイム:お盆にちなんで「おじいちゃんおばあちゃんと何をした?」など、家庭とのつながりを振り返る時間を持つことも大事です。
まとめ
お盆は、日本人にとって「いのち」や「家族のつながり」を大切に思う行事です。
保育の中でも、お盆をきっかけに「ありがとうの気持ち」や「目に見えない存在への思いやり」を育むことができます。
地域や家庭によって過ごし方はさまざまですが、共通しているのは「たいせつな人を思う心」。子どもたちと一緒に、あたたかく伝統を学び、感じる時間を作っていきましょう。