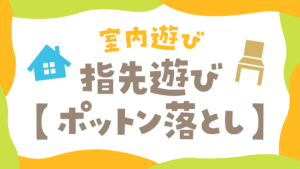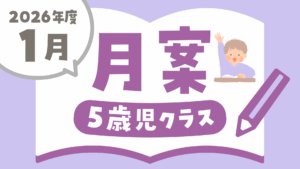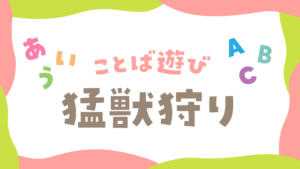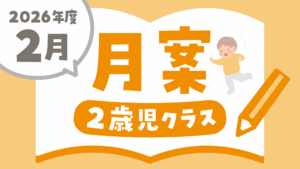9月1日は「防災の日」。毎年この時期になると、災害への備えや安全について見直すきっかけになります。特に小さな子どもを預かる保育の現場では、いざというときの行動が命を守る大きなカギに。今回は「防災の日」とは何か、その由来や子どもたちへの伝え方、そして保育現場で実践できる活動について、分かりやすくご紹介します。
「防災の日」とは
「防災の日」は毎年9月1日に設けられた、災害への備えを見直すための日です。地震や台風、火災などの自然災害に対して正しい知識を持ち、命を守るための行動をとれるようにすることを目的としています。
全国の学校や保育園、公共機関などでは避難訓練や防災教育が行われ、地域でも防災意識を高める様々な取り組みが見られます。この機会に、ご家庭や園でも「備える力」を育む時間を持つことが大切です。
防災の日の由来
防災の日が制定されたのは1960年。由来は1923年9月1日に発生した「関東大震災」にあります。死者・行方不明者14万人以上といわれる甚大な被害を出したこの地震は、日本の防災意識に大きな影響を与えました。政府はこの日を「災害への備えを考える日」として定め、全国的な防災訓練が行われるようになりました。
ただし、「9月1日」は台風の被害が多い時期ということもあり、複合的な理由から選ばれたとする説もあります
※出典:内閣府防災情報ページ

子どもへのわかりやすい説明
2歳児への説明
2歳児には「防災の日」という言葉自体が難しいため、まずは
「地震がくると、びっくりすることがあるよ」と安心できる語り口で話すことが大切です。
防災の日は
「みんなで逃げるを練習する日だよ」とシンプルに伝えましょう。
紙芝居やぬいぐるみを使って、「ぐらぐらってなったら こうするんだよ」と避難動作を見せると理解が深まります。由来に関しては触れず、「怖くないように 準備を する日」とイメージづけするのが良いでしょう。
3歳児への説明
3歳児には
「防災の日は、地震や台風のときの練習をする日だよ」と、少し踏み込んだ内容が伝えられます。たとえば、
「おうちや 園が 揺れたら どうする?」と問いかけながら話を始めると、子どもも興味を持ちます。
防災の日の由来は
「むかし、沢山の人が 地震で 困ったから、これからは 準備しようねって 決めたんだよ」
と、優しく語りましょう。
災害の被害よりも「みんなが元気でいられるためにある日」という前向きな伝え方を意識すると安心感につながります。
4歳児への説明
4歳児には「防災の日は、むかしあった 大事なできごとを 忘れないための日」という視点が伝えられます。
「毎年 9月1日に 練習をして、みんなの 命を 守る 準備を するんだよ」と伝えることで、記念日の意味も理解しやすくなります。
由来に関しては、
「100年くらい前にとても大きな地震があって、たくさんの人が大変だったの。だからこの日が できたんだよ」
と、歴史的背景をかみくだいて説明します。絵地図や模型を使いながら話すと理解が進みます。
5歳児への説明
5歳児には「防災の日」は「自分や 周りの人の 命を 守るための 大切な日」という概念まで踏み込めます。
「どうして防災の日があるの?」という問いに、
「むかし、沢山の人が地震で亡くなってしまったことがあって、これからは そうならないように 練習することにしたんだよ」
と伝えましょう。
関東大震災の話も「東京や 横浜というところで 大きな地震があった」と、具体的な地名を出して話すことで現実味が増します。話のあとに子どもたちから意見や感想を聞く時間を設けると、学びが深まります。

防災の日に関連する情報
防災の日に関連する保育の取り組みとして、日常的な備えの見直しも大切です。
たとえば「非常持ち出し袋の点検」や、「アレルギー対応の備蓄食品の確認」、「保護者との連携体制の再確認」などがあります。また、子どもが災害時に不安にならないよう、日常的に「防災」を身近に感じられる絵本や紙芝居、歌などの活用も有効です。
「じしんだ!」「おかしも(お=おさない、か=かけない、し=しゃべらない、も=もどらない)」などの標語を取り入れた遊びやクイズもおすすめです。
防災の日にちなんだ保育活動
⚫︎避難訓練の実施:実際にサイレンを鳴らして行う訓練や、年齢に応じた「だんごむしポーズ」「おかしもルール」の確認など。
⚫︎防災製作あそび:紙皿で防災ヘルメットを作る、非常持ち出し袋を模したカバンづくりなどを通じて「備えること」を楽しく体験。
⚫︎紙芝居や読み聞かせ:地震・火事をテーマにしたお話を読んだり、登場人物と一緒に「どうする?」を考える時間を持つ。
⚫︎防災リレーごっこ:「地震がきたら?」をテーマにした動きのある遊びで、体を動かしながら自然に避難行動を学べる活動です。
まとめ
「防災の日」は、子どもたちの命を守るために大人が何をすべきかを改めて考える大切な機会です。
保育現場でも、怖がらせることなく、楽しく・わかりやすく伝える工夫が求められます。
年齢に応じた関わり方を通じて、「自分の身を守る力」を育てていきましょう。
園だけでなく、ご家庭とも連携しながら、日常の中に防災意識を育むことが、子どもたちの未来を守る第一歩になります。