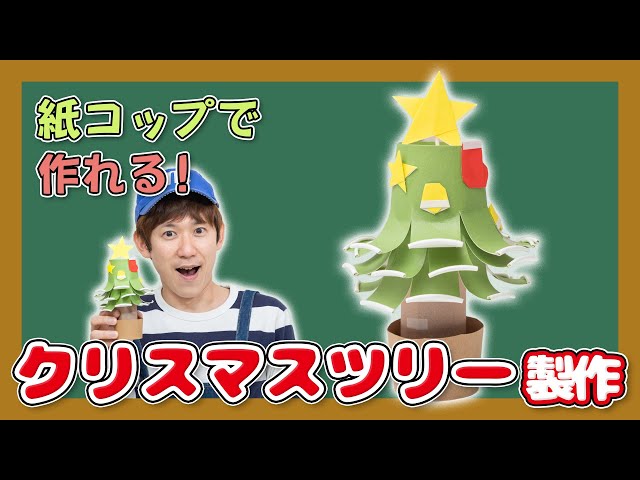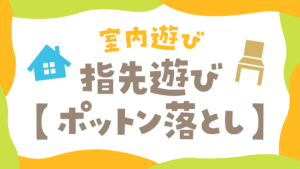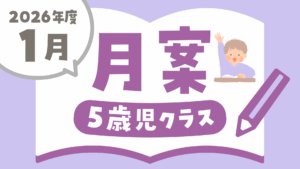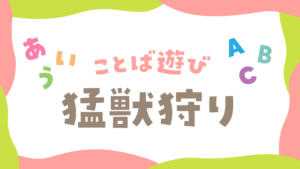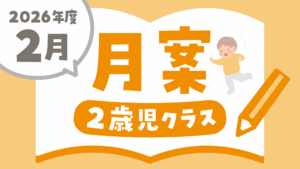12月になると、街中にきらめくイルミネーションやツリーが並び、子どもたちも楽しみにする「クリスマス」がやってきます。
サンタクロースやプレゼント、おいしいごちそうなど、ワクワクが詰まった季節の行事ですが、その背景には大切な由来や意味もあります。
今回は「クリスマスとは何か」「どうして祝うのか」をわかりやすくまとめ、子どもへの伝え方や保育に役立つ活動アイデアをご紹介します。
クリスマスとは
クリスマスは、イエス・キリストの誕生を祝う日として、毎年12月25日に行われるキリスト教の祝祭です。
宗教行事が起源ですが、現在では世界中で「家族や大切な人と過ごす日」「子どもたちが楽しむ行事」として親しまれています。
日本では明治時代に伝わり、戦後に一般家庭でも広まったとされています。
保育の場では、異文化理解や「誰かに喜んでもらうことの大切さ」を伝える機会として取り入れる園も多く、季節感を楽しむ行事として定着しています。
クリスマスの由来
クリスマスは、紀元前から続く「冬至のお祭り」や「光の復活を祝う行事」と、キリスト教の信仰が結びついて生まれました。
キリストの正確な誕生日は聖書に記されていませんが、ローマ時代に「太陽の復活を祝う日(冬至祭)」と重ねる形で、12月25日がイエス誕生を祝う日と定められました。
サンタクロースのモデルは、4世紀に実在した「聖ニコラウス」という司教で、子どもや貧しい人を助けた優しい心が、現在の「プレゼントを届けるサンタさん」として伝わっています。

子どもへのわかりやすい説明
2歳児
2歳児には
「クリスマスは、サンタさんがプレゼントをくれる日だよ」
と、シンプルに楽しい行事として伝えます。
「おうちやほいくえんでツリーをかざって、みんなでケーキを食べる日」
と具体的に話し、生活に結びつけましょう。由来は触れず、ワクワク感を大切にします。
3歳児
3歳児には
「クリスマスは、おうちのひとやおともだちと“ありがとう”のきもちをわけあう日」
と伝えると良いでしょう。
「サンタさんは、むかしから ずっとこどもたちに プレゼントを とどけてくれているんだよ」
と、サンタクロースの由来を簡単に紹介すると理解が深まります。
4歳児
4歳児には
「クリスマスは、イエスさまというひとがうまれたことをおいわいする日なんだよ」
と、宗教的な意味もやさしく説明できます。
「むかしのひとたちは、ひかりがもどってくるのをおいわいしていたんだよ」
と冬至とのつながりを加えると、自然への理解も広がります。
5歳児
5歳児には、歴史や文化的背景を少し詳しく伝えます。
「キリストというひとが、みんなをしあわせにするために生まれたんだよ」
「サンタさんは、よいこにしているみんなを ちゃんとみていて、クリスマスのよるに プレゼントを とどけてくれるんだよ」
と話すと、物語として興味を持ちやすいです。
異文化理解や「人にやさしくする心」がテーマになるように導きましょう。

関連情報
他にもクリスマスに関連する様々な由来をみてみましょう。
【クリスマスツリー】
クリスマスツリーの起源は、冬でも葉を落とさない常緑樹を「生命の象徴」として飾った古代の風習にあります。
中世ドイツでは宗教劇や家庭でモミの木を飾る習慣が生まれ、19世紀にヨーロッパから世界へ広がり、今の形になったといわれています。
【星(トップオブスター)】
クリスマスツリーの星は「ベツレヘムの星」が由来といわれています。
イエス誕生のとき、東方の博士を導いた星とされ、救い主の誕生や人々を導く希望の象徴としてツリーの頂点に飾られています。
【クリスマスリース】
クリスマスリースは、常緑樹を円形に束ねたのが始まりで、終わりのない「永遠の命」や「希望」を象徴します。
ドイツで家庭の扉に飾られ、家族を守る魔除けの意味も込められました。
現在では平和や幸福を願う飾りとして広く親しまれています。
【ベル】
クリスマスのベルは、イエス誕生を知らせる喜びの音として広まりました。
教会では礼拝や祝祭の合図に鐘を鳴らし、人々にキリストの誕生を告げました。
また、ベルの音には「魔除け」や「平和を呼ぶ」という意味も込められています。
【トナカイ】の由来
クリスマスのトナカイは、19世紀の詩「サンタクロースがきた」でサンタのそりを引く存在として広まりました。
寒冷地に住むトナカイは力強さや耐久力の象徴で、サンタの旅を助ける仲間として描かれ、子どもたちに夢を与える象徴的な動物となりました。
【赤い丸(クーゲル)】
クリスマスツリーの飾り「クーゲル」は、16世紀ドイツでリンゴの代わりにガラス職人が作った球形の装飾が始まりです。
豊かさや実りを象徴し、やがて色とりどりのガラス玉として世界に広まり、現代のオーナメントの原型となりました。
【ろうそく】
クリスマスのろうそくは、冬の闇を照らす「光」として古代の風習から受け継がれました。
キリストを「世の光」とする信仰と結びつき、希望や導きを象徴します。マルティン・ルターがツリーにろうそくを灯した逸話も広まり、定着しました。
【杖(キャンディケイン)】
クリスマスの杖(キャンディケイン)は、羊飼いの杖をかたどったものが由来です。
羊を導く杖はイエスを導く象徴とされ、白は純潔、赤はキリストの血を表すともいわれます。
やがて甘い菓子として作られ、子どもたちに配られるようになりました。
クリスマスにちなんだクラス活動アイデアを年齢別にご紹介
クリスマスの由来を子どもたちにわかるように解説した後は、クラス活動に取りかかりましょう。ここでは年齢別に制作した後も使える作品をご紹介しています。楽しいクリスマス制作の参考にしてくださいね。
乳児向け
乳児のクリスマス制作では月齢にあった材料を使いましょう。また完成した後も扱いやすい作品にすることで保護者にも喜ばれますよ。
【クリスマスブーツ】
定番の制作ですね。ブーツの形に切った画用紙を張り合わせて中が入るようにすれば、プレゼントを入れることもできます。飾りつけにはスポンジでつくったスタンプ、シール、マスキングテープなど様々な材料が使えますね。
【クリスマスリース】
紙皿の真ん中をくり抜くと簡単にリースの形が作れます。カラースプレーで着色してもいいですし、子どもたちと一緒に絵の具で色塗りしてもいいですね。リボンを使って下げられるようにするとおしゃれになりますよ。
幼児向け
サンタさんやプレゼントを楽しみにしているこの年齢は、よりクリスマス気分が盛り上がるグッズがおすすめです。普段のごっこ遊びでも使えそうですね。
【サンタの帽子】
色画用紙はもちろん、不織布やカラーポリ袋で作っても可愛い帽子ができあがります。形を作る前の段階でデコレーションしておくと、きれいに成形できますね。
【ハンドベル】
小さいペットボトルに鈴を入れます。キャップをつけた飲み口をビニールテープやリボンで巻いたら、ハンドベルの完成です。鈴以外にビーズを入れると音が変わって子どもたち同士で音を鳴らして楽しむことができますよ。
手先が器用になってきているこの時期はちょっと完成度の高い制作がおすすめです。材料には普段使わないものもありますので、保育士が必ず見守りながら制作を行いましょう。
【クリスマスツリー】
手芸用の小さなポンポンをツリー型になるようにボンドでくっつけていきましょう。乾いたらスパンコールやビーズをつけていきます。見た目が可愛くておしゃれですので、保護者受けもよい制作です。
【スノードーム】
空き瓶に入るぐらいの小さなミニチュアやお花などを用意します。ビンに飾りたいものを接着剤(グルーガンなど)で設置します。完全に接着剤が乾いたら、洗濯のりと水を7:3の割合でまぜた液体をゆっくりそそぎましょう。その後、スノーパウダーをビンに入れて、しっかりフタを閉めたら完成です。
その他 クリスマスにちなんだ保育活動
- クリスマスカード作り:手形や折り紙を使ってオリジナルカードを制作し、家族に「ありがとう」の気持ちを届ける。
- サンタごっこ:プレゼントを届ける役・受け取る役になって遊ぶ。
- 世界のクリスマス紹介:簡単な絵本や写真を使って、各国の過ごし方を知る。
- クリスマス会:歌や劇、クイズなどを盛り込み、子どもたち全員が参加できる楽しい行事に。

まとめ
クリスマスは、子どもたちにとって楽しいだけでなく、「感謝」「分かち合い」「やさしい心」を育む行事です。
由来を知ることで、ただのイベントではなく、歴史や文化を学ぶきっかけにもなります。
保育の中では、子どもたちが自分なりに「ありがとう」を表現できるような活動を取り入れることで、心温まる体験になります。
今年のクリスマスは、園や家庭で笑顔と感謝の気持ちを分かち合ってみませんか?