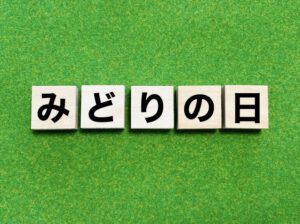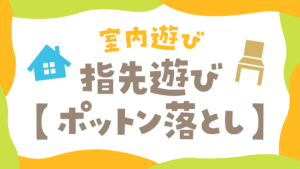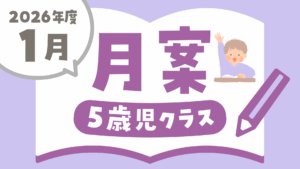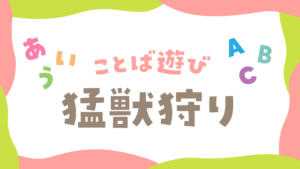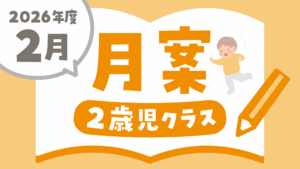お月見は童謡「うさぎうさぎ」でも登場する、子どもたちになじみのある行事ですね。
お月見の日にお団子を食べること、ススキを飾ることは子どもたちにも知られています。
しかし、お月見の由来についてはあまり知られていないかもしれません。
お月見は制作やクラス活動にも取り入れやすい題材ですので、ぜひ由来を子どもたちに説明できるようなりましょう。
「お月見」とは
「お月見」は、秋の満月を愛でながら、豊かな実りに感謝する日本の伝統行事です。
一般的には旧暦の8月15日(現在の9月中旬〜10月初旬)に行われ、「十五夜」と呼ばれます。
この日は空気が澄み、月が最も美しく見えるとされ、すすきを飾り、月見団子や秋の収穫物をお供えして月を眺めます。
また、「十三夜」(旧暦の9月13日)も親しまれており、両方を楽しむ地域もあります。行事を通じて、自然の恵みに感謝する心を育むことができます。
お月見の由来
お月見の起源にはいくつかの説があります。
奈良〜平安時代、中国の「中秋節(ちゅうしゅうせつ)」の影響を受けたと言われています。
当時の貴族たちは、月を眺めながら詩を詠み、風流を楽しむ行事として親しんでいました。
一方で、日本独自の農耕儀礼とも結びつき、秋の収穫を祝う「収穫祭」の一環として月に感謝を捧げるようになったという説もあります。
つまり、お月見は「自然への感謝」と「季節を楽しむ文化」が融合した、日本らしい行事なのです。

子どもへのわかりやすい説明
2歳児への説明
2歳児には「お月見」という言葉や意味は難しいため、絵本や歌を通して「まんまるおつきさま」を楽しむことが大切です。
「きょうは、おつきさまに“こんにちは”するひだよ」
「おつきさま、にこにこしてるね」
と声をかけることで、お月見を“特別な夜”として印象づけられます。
由来には触れず、団子やすすきなどを「きれいだね」「おつきさま、よろこんでるかな」とイメージしやすい言葉で伝えましょう。
3歳児への説明
3歳児には
「お月さまをみて、“ありがとう”っていうひなんだよ」
と、感謝の気持ちを込めた説明が効果的です。
絵カードや写真を見ながら、
「すすきは、おつきさまのおはな。おだんごは、おやつみたいな おそなえもの」
など、視覚的に楽しく伝えましょう。
由来については、
「むかしのひとたちは、おつきさまをみて うたをよんだり、ありがとうっていったんだよ」
と、やさしい言葉で伝えると、伝統行事への親しみが育ちます。
4歳児への説明
4歳児には、
「おつきみは、あきに おいしいたべものが とれたことに かんしゃする ぎょうじなんだよ」
と伝えられます。
絵本や紙芝居を用い、
「おつきさまは、はたけのかみさまだったんだよ」
とストーリー仕立てにすると興味を持ちやすくなります。
由来については
「ちゅうごくの ひとたちが おつきさまに おいのりをするひがあって、それが にほんに つたわったんだよ。でも、日本では たべもののありがとうのひにも なったんだ」
と説明すると理解しやすいです。
5歳児への説明
5歳児には、お月見の意味や由来をより具体的に説明できます。
「お月見は、むかしの人が つきのうつくしさをたのしんだり、たべものがたくさんとれたことに ありがとうっていう行事なんだよ」
と話すと、行事の意義が伝わります。
由来についても、
「ちゅうごくの ちゅうしゅうせつっていうぎょうじが、にほんにきて、のうかの人たちが“しゅうかくのおいわい”としても おこなったんだよ」
と歴史の流れも加えると、文化理解が深まります。活動の前に子どもたちと一緒に話し合う時間を設けるのもおすすめです。

「お月見」に関連する情報
お月見は、保育の現場において「自然の恵みに感謝する気持ち」や「季節のうつろいを楽しむ心」を育てる絶好の機会です。
導入としては、秋にちなんだ絵本の読み聞かせや、歌(例:「つき」「うさぎ」など)を取り入れると、子どもたちの関心を惹きつけやすくなります。
また、家庭での過ごし方や地域の風習について、保護者にアンケートをとることで家庭連携にもつながります。園便りでお月見の意味や過ごし方を紹介するのも効果的です。
お月見をきっかけに、月や自然への興味を広げる活動を展開しましょう。
「お月見」にちなんだ保育活動
お月見に関連する保育活動は、行事の意味を体験として伝えることが大切です。
- お月見製作
紙皿で満月を作ったり、ちぎり絵で団子やすすきを描く活動。制作を通じて行事のモチーフに親しめます。 - お団子づくりごっこ
実際に団子を作るか、粘土や小麦粉粘土で模擬的に作る。手先の発達と伝統理解を両立。 - おつきさまの観察
晴れた日に月を見上げたり、イラストや図鑑で月の形を学ぶ活動。月の満ち欠けにも興味が向くきっかけになります。 - おつきみ会ごっこ
お供えを飾り、子どもたちと「おつきさまにありがとうを言う会」を開催することで、行事を楽しく体験できます。
まとめ
お月見は、日本の四季や自然を大切にする文化が詰まった美しい行事です。
保育の中で子どもたちに「季節を感じる心」「感謝の気持ち」を育むよい機会となります。
難しい由来も、年齢に応じてやさしく、楽しく伝えることで、伝統行事への親しみが深まります。
今年のお月見は、空に浮かぶ満月と一緒に、子どもたちと“ありがとう”の気持ちを伝える時間にしてみませんか?