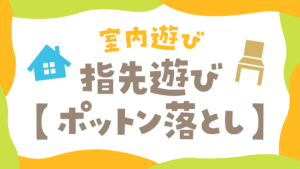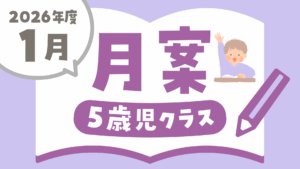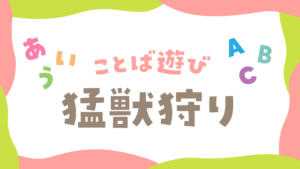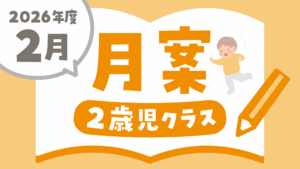このノートでは、こどもといきいきした会話を築くためのちょっとしたコツを紹介します。でも、あんまり気にしないでください。なによりも会話は力みすぎないことが大事。ちょっと頭の片隅に置いておくことで、ちょっぴり役に立つ、隠し味的なお話です。
凄いって言ってない?
こどもが何かをしたとき、とにかく誉めないといけないと考えていたら、「凄い」という言葉はとても便利な言葉です。人間が何かをして、凄くないわけがありません。「凄いね」と言ってあげると、こどもも満足してきっと喜びます。
ただそこで少し考えてみてください。こどもを誉めて、私たちは何を求めているのでしょうか?もう一度、こどもが同じことをしたら、それは凄いことでしょうか?凄いことは良いことなのでしょうか?
大人の価値観でこどもをみない

凄いことは、いったい何が凄かったのでしょうか?大人が勝手に凄いと評価をしているのは、大人が勝手に決めた基準です。もしかしたら、こどもは「まだまだこんなことで満足してられない!」と思っているかもしれません。
こども自身が凄いと言って欲しいにしても注意がいります。凄いことが良い関係は、こどもが大人に認めてもらわないといけない関係です。それは、大人の世界にこどもが合わせ、こどもが自由にものを考える関係ではありません。
もちろん、大人にも事情があって、こどもに合わせてもらうことも必要です。でも、それはこどもが自由に考えられる環境を守るために必要なのです。これまでのノートをぜひ参考にしてください。
私たちの目標は、こどもが大人になるにつれて主体的にものを考え、創造的に社会を発展させていくことです。(ですよね?)私たち大人も自分の価値観を持っていることは当然必要なこととして、こどもに対しても、どんな基準や価値観を持っているのか関心を持つことが大切です。
凄いねと言う代わりに
それでは、どうしたら良いのでしょうか?それは先にも述べたように、関心を持つことです。こどもが何かをしたとき、まずは事実に関心を向けます。「○○ができたね」「○○が○○になったね」などなど。
こどもと事実を共有します。事実を共有することが、こどもを受け入れ肯定することに繋がります。事実を共有することができたら、こどもは次の展開を考えやすくなります。
大人が評価付けをしない分、どのような展開もこどもの自由です。こどもが評価を求めてくることもあります。「凄い?」と聞かれたら、先ほどと同じように事実の共有をしてみるのもありです。
ほかには、「どう?」と関心をもって聞いてみるのもひとつの手です。するとこどもから「○○が○○した」など事実の共有があるかもしれません。それでも、評価を求められたら、こどもが求めている評価を伝えます。「○○ができるって○○だね」「いまの○○は○○だね」などなど。大人がこどもの評価基準に合わせていく姿勢が重要です。