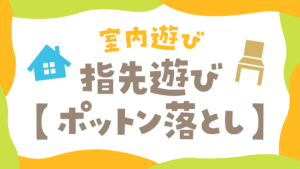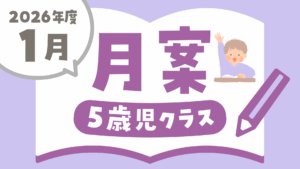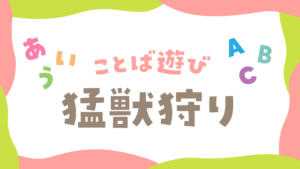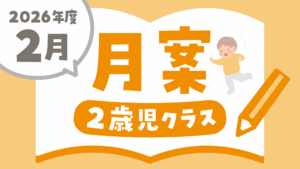このノートでは、こどもといきいきした会話を築くためのちょっとしたコツを紹介します。でも、あんまり気にしないでください。なによりも会話は力みすぎないことが大事。ちょっと頭の片隅に置いておくことで、ちょっぴり役に立つ、隠し味的なお話です。
こどもにして欲しいことがあるとき
日常、こどもにこれをして欲しい、あれをして欲しいと思うことがあります。
あまり保育園の現場ではないかもしれませんが、家庭ではこどもにも協力してもらわないと生活がまわりません。 「○○してね」とお願いしても、こどもは思ったように動いてくれません。とくにイヤイヤ期のこどもならなおさらです。
こどもが求めている主体性

そもそもこどもはなぜ、「イヤ!」というのでしょうか?
こどもは、自立に向かって成長しています。自立のためには、基本自分でなんでもできるようにならないといけません。こどもはいつか来る自立のために、自分でなんでもやりたいようにできています。
だから、大人に言われたことはイヤ!と感じるのです。とても大切なことですね。
言われた通りに動いているのでなく、自分で考えて行動していると思える工夫があれば、こどもは大人の声に耳を傾けやすくなります。
選択肢を用意しよう
工夫のひとつは、こどもが選択できるように声をかけることです。
こどもはどちらをするか選ぶことができるので、自分で考えて行動していると実感できます。「お片付け、絵本ないないする?それともブーブーないないする?」(片付けをして欲しい時)「どの子(ぬいぐるみ)とねんねする?」(寝かしつけの時)などなど、工夫の仕様はたくさんあると思います。
この時、大事なのはどちらを選んでもいいことです。
「寝るの?寝ないの?」と問いかけたとき、こどもが寝ないと答えたら、困りますよね。
先ほどの例で言うと、絵本を選んでも、ブーブーを選んでも片付けをすることにかわりはありません。寝かしつけの例でも同じです。
「今日はどの子(ぬいぐるみ)と寝ようか?」という、質問はどのぬいぐるみを選んでも大丈夫です。
「うーん。この子!」ぬいぐるみを選んで寝ることに意識が向いたら、「じゃあ、寝室にいって、その子ねんねしようか」「うん」、と寝かしつけの言葉も入りやすくなります。
選択できるような声かけはバリエーションが豊富です。ぜひ、いろいろ考えてみてください。