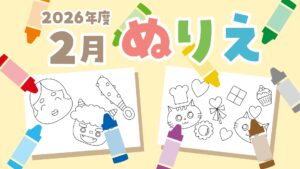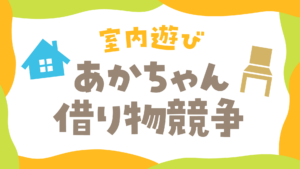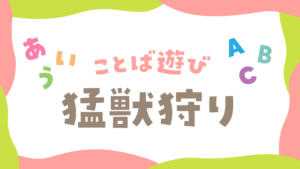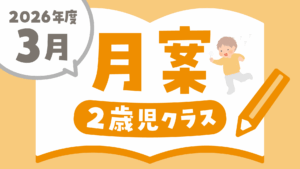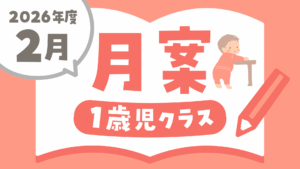ハロウィンは日本でも秋の一大イベントになりましたね。子どもが興味をもちやすいハロウィンはクラス活動にぜひ取り入れたいところ。そんなハロウィンの活動にとりかかる前に由来について子どもにわかりやすく説明したいですよね?
ですが、もともとは外国のイベント。由来は少しめんどうな感じがしませんか?この先を読めばすぐに「ハロウィンの由来」「なぜお菓子がもらえるようになったのか」「ハロウィンで仮装をする理由」について子どもたちに説明できるようになりますよ。
ハロウィンとは
ハロウィンは、毎年10月31日に行われるお祭りで、もともとはヨーロッパの古代ケルト人の収穫祭「サウィン祭」が起源とされています。
秋の収穫を祝うと同時に、死者の霊がこの世に戻ってくると信じられていたため、悪霊を追い払う儀式も行われていました。
現在ではアメリカでの普及を経て「仮装してお菓子をもらうイベント」として定着し、日本でも秋の行事のひとつとして楽しまれるようになっています。保育園でも、異文化理解や季節感を学ぶ良い機会として活用できます。
ハロウィンの由来
ハロウィンの起源は、古代ケルト民族が行っていた「サウィン祭」にあります。
これは1年の終わりとされていた10月31日に、先祖の霊が戻ってくると信じられていた風習で、人々は仮装をして悪霊から身を守ったとされています。
のちにキリスト教の「万聖節(All Saints’ Day/11月1日)」の前夜祭として取り入れられ、「All Hallows’ Eve」が短縮されて「Halloween」になりました。現在のような形に変化したのはアメリカでの風習が発展したことによります。
こうした背景を知ると、ただの仮装イベントではなく、文化理解の一環としての価値も見えてきます。

トリック・オア・トリートの意味
「お菓子をくれないと、いたずらするぞ」という意味です。おやつのない家はおばけがいたずらをしてもいいことになっています。トリック・オア・トリートと言うことで、いたずらをしてもいいか確認することができるのですね。
ハロウィンで仮装する理由
ハロウィンの日、おばけは人間をあの世に連れていこうとすると考えられていました。なので、人間だと気づかれないようにおばけに仮装するようになったがはじまりです。また仮装をすることで、本物のおばけがびっくりして逃げていくためでもありました。だからちょっぴり怖いおばけに仮装するのですね。

かぼちゃのランタンを飾る理由
かぼちゃのランタンを玄関においておくと、魔除けになると言い伝えられているからです。かぼちゃのランタンは英語で「ジャック・オ・ランタン」とよばれています。日本語にすると「ジャックのランタン」という意味になります。
ジャックという男の人がおばけをだましたバツとして、死んだ後、天国にも地獄にもいけずランタンを持ってさまよっている、というおはなしが元になっています。
子どもへのわかりやすい説明
2歳児への説明
2歳児には
「ハロウィン」は「かわいいおばけになって、みんなで“トリックオアトリート”って言う日だよ」
と楽しい雰囲気で伝えましょう。
怖さは避け、仮装やお菓子をもらう遊びに焦点を当ててください。
「おばけさんにへんしん!」「おかし、もらえるかな?」
といった言葉かけでワクワクする気持ちを引き出せます。
由来には触れず、非日常を楽しむ体験を大切にします。
3歳児への説明
3歳児には
「ハロウィンは、おばけのまねっこをして、おともだちとあそぶ日なんだよ」
と遊び感覚で伝えましょう。
「むかしむかし、よるになると わるいおばけが くるって いわれてて、みんな おばけのふりをして にげたんだって」
と簡単に伝えることで、背景にも少し触れられます。
こわくなりすぎないように、「おばけごっこ」「かぼちゃさんにへんしん」など、かわいらしい仮装を通じて安心感をもたせましょう。
4歳児への説明
4歳児には
「ハロウィンは、むかしの人たちが“おばけにまちがわれて つれていかれないように”って へんそうをしたのが はじまりなんだって」
と、物語として由来を伝えることができます。
「かぼちゃに かおをつけて、おばけを おいはらったんだよ」
とジャック・オー・ランタンの話につなげると、さらに興味を持ちやすくなります。
絵本や仮装制作を通して、
「ハロウィンってたのしいだけじゃなくて、むかしの人の ちえがあるんだね」
と文化理解につなげていくとよいでしょう。
5歳児への説明
5歳児には、
「ハロウィンは むかしの人たちが、あのよから かえってくるれいを むかえるための ぎょうじだったんだよ」
と、より歴史的な側面に触れることができます。
「かぼちゃのなかに ろうそくをいれて、こわいかおをつくって おばけをおいはらったんだよ」
というように、行事の意味や理由をしっかり伝えられます。
また、「どうして“トリックオアトリート”っていうの?」など、子どもたちの疑問に答えながら、会話の中で理解を深めることができます。

関連情報
ハロウィンは異文化行事であるため、導入の際は「楽しさ」と「文化的背景」の両方をバランスよく伝えることが大切です。
保育の場では、宗教的要素を避けつつ、「海外の秋のお祭り」として扱うことが一般的です。
絵本や英語の歌(例:”Five Little Pumpkins”や”Knock Knock, Trick or Treat?”)を取り入れることで、異文化への親しみも自然に育まれます。
保護者にも、仮装やお菓子の取り扱いについて説明を添えると安心して協力してもらえるでしょう。
アレルギー対応や安全面にも十分配慮しながら行事を楽しむことが大切です。
ハロウィンにちなんだ保育活動
保育現場で取り入れられるハロウィン活動は多彩です。
- 仮装パレードごっこ:園庭や室内で「かぼちゃ」「こうもり」「ねこ」などに仮装してパレード。衣装はマントや帽子など簡単なものでもOK。
- おばけのお面づくり:紙皿や画用紙で「かわいいおばけ」や「かぼちゃの顔」を工作。
- トリック・オア・トリート遊び:先生たちが「お菓子屋さん役」になり、子どもたちが合言葉でお菓子(またはカードなど)をもらう遊び。
- ハロウィン壁面製作:子どもたちの作ったかぼちゃやおばけを飾って、季節感を楽しむ。
年齢に応じて無理のない内容に調整し、行事を「楽しい+学びのある」時間にできるよう工夫しましょう。
まとめ
ハロウィンは、子どもたちにとって「変身して遊ぶ」「お菓子をもらう」楽しい行事であると同時に、異文化に触れる貴重な学びの機会でもあります。
由来を知り、意味を考えることで、ただのイベントではなく“心の成長”につながる時間となるでしょう。
保育の中では、子どもが安心して楽しめる工夫をしながら、季節や文化の多様性を感じられるような取り組みをしていきましょう。