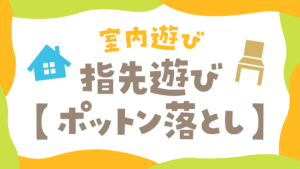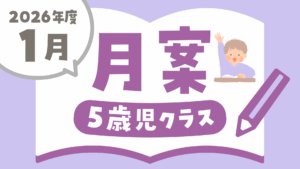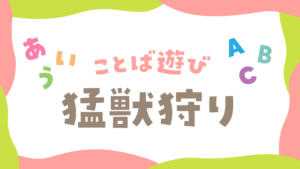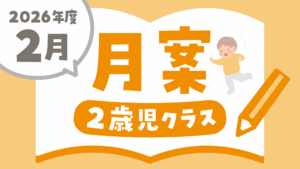子育てをしている方なら誰もが一度は経験したことのある「子どもの夜泣き」は、様々な原因があります。深夜に大きな声で泣く姿を見ると、近所迷惑にならないだろうかと心配になったり、早く泣き止ませなきゃという気持ちになって焦ってしまいますよね。 今回は子どもの夜泣きの原因と対処法についてわかりやすくお教えしていきます。夜泣きの原因と対処法をいくつか理解しておくだけで、気持ちに余裕ができるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
子どもの夜泣きの原因は?
ぐっすり寝ていたと思ったら、急に大きな声を出して泣く「夜泣き」にはいくつかの原因があると言われていますが、確実に「これだ!」という明確な答えはありません。
子どもと過ごす日々の中で、もしかしたらこれが原因かも?と思い当たる部分を見つけ出せるかもしれないので、子どもの様子をよく観察することが大事になってきます。
夜泣きは生後3ヶ月から1歳半頃の子に起きやすい
まず、夜泣きをする月齢としては生後3ヶ月から1歳半頃の子に多いと言われています。
子どもの成長はそれぞれペースが違うので一概には言えませんが、2歳をすぎても夜泣きする子もいれば全く夜泣きをしないという子もいるようです。夜泣きは成長する上で誰もが通る道だと理解して、不安になりすぎないようにしましょう。
夜泣きは生後3ヶ月から1歳半頃の子に起きやすい
子どもの成長や発達にそれぞれ違いがあるように、夜泣きの原因も様々です。ですが、多くの場合、夜泣きの原因は「子どもの体や脳の成長過程と関連があるのではないか」と考えられています。
生後3ヶ月から6ヶ月までの赤ちゃんは、体内時計が未熟で睡眠のリズムがうまく取れず夜泣きに繋がりやすいです。
また、脳が急激に発達する時期でもあるので、日中の刺激も受けやすく、睡眠中に脳が処理しきれなかった結果、夜泣きが起きると言われています。
生後半年から1歳半ごろの子どもは、断乳や卒乳の時期を迎え授乳がなくなったことのストレスで夜泣きをしたり、生活リズムが崩れ上手く睡眠できない時に起こりやすいようです。
睡眠時の環境や衣類によって夜泣きが起きる
睡眠時の室内環境も、夜泣きに繋がる原因のひとつとなります。
寝室が寒すぎたり暑すぎたり、湿度が高くじめじめしていると子どもも寝苦しく夜泣きが起きやすくなります。また、子どもの着ている衣類も重ね着しすぎて暑く動きづらかったり、リラックスできないと不快感から起きてしまうこともありますよ。
体調不良時は夜泣きが多い

子どもの成長過程において起きる夜泣きとは別に注意しなくてはいけないのが「体調不良時の夜泣き」です。
夜泣きが続いている時期は子どもが泣いても「また普段の夜泣きかな?」と思ってしまいますが、体調不良のサインの可能性もあります。子どもが泣いたらまずは肌に触れて熱がないかの確認をしましょう。
子どもの夜泣きの対処法
子どもの夜泣きは成長過程の月齢によって原因に違いがあったり、環境や体調など気にかけなくてはいけない点が見えてきましたね。
夜泣きの原因にいくつか思い当たる部分があれば、対処しやすくなるでしょう。
すぐに抱っこせずトントンしながら様子を見る
夜泣きが始まったら「早く泣き止ませなきゃ!」という気持ちで、ついすぐに抱っこしてしまいがちですが、泣き始めた時はトントンしながら少し様子を見ましょう。そのまま安心して寝てくれる場合もあります。
様子を見ていても夜泣きがおさまらなかったり、激しく泣く場合は抱っこして落ち着かせてあげます。名前を呼んで、一度目を覚ましてあげると子どももふと我に返って落ち着くことが多いです。
衣類の調整、水分補給を行う
汗をかいていたりオムツが汚れていたら、着替えてオムツ替えをしましょう。
暑くて不快な気分だったのが気持ち良くなり、スッと再眠できる体勢になります。卒乳、断乳からのストレスで夜泣きをしている子には水分補給も効果的です。おっぱいやミルクの代わりにお茶や水を飲むことで落ち着くことができますよ。
生活リズムを整え、活動的に過ごす
眠りやすい環境を作るためにも、生活リズムを整えることが大切です。
朝は7時までに起きて、しっかり太陽の光を感じましょう。朝食をとったら日中は散歩や外遊びをして活動的に過ごすと身体もほどよく疲れ、入眠しやすくなります。
お昼寝の時間も、夕方にずれ込んでしまったり長時間寝かせすぎると夜の入眠時間が遅くなってしまうので、上手に調節していけると良いですね。
入眠儀式を作り、安心して眠れる環境を整える

自然に入眠できるよう「入眠儀式」を作ると、子どもも「寝る時間なんだ」と体で覚えて、落ち着いた気持ちで布団の中に入ることができます。
入眠儀式の例としては「お風呂→歯磨き→絵本の読み聞かせ→オルゴール音楽をかける→入眠」といったように毎日同じ順番で寝かしつけを行います。
ルーティン化することで子どもも少しずつ覚えていくので、可能な限り入眠儀式を取り入れていくことをおすすめします。
また、寝る前にたくさんスキンシップを取ることも大切です。手を握ったり、頬を撫でると安心して眠りにつくことができますよ。
まとめ
子どもの夜泣きの原因と対処法についてお話ししてきました。夜泣きの原因としては個人差もあり明確な答えはありませんが、成長過程でのものだったり、環境や体調によるものだったりといくつか考えることができます。
夜泣きを完全に止めるのは難しいですが、必ずいつかは終わりがくるものなので、周囲に頼りながら夜泣きの時期を乗り越えていきましょう!