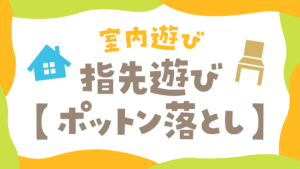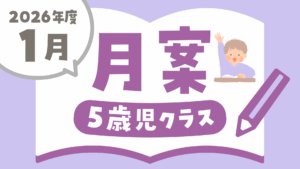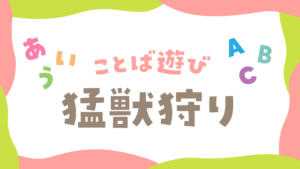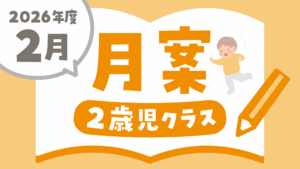新しい年のはじまりをお祝いする「お正月」。
おせち料理や年賀状、初詣など、たのしい行事がたくさんありますね。
でも、それぞれどのような成り立ちで現在の行事になったのかはご存じですか?
この記事では「お正月とはなにか」から、その由来や保育での活かし方、子どもへの伝え方までを、やさしく解説します。
読み終えるころには「お正月」がもっと身近で、大切なものに感じられるはずです。
お正月とは
「お正月」は、1年のはじまりを祝い、無事に過ごせるように願う日本の伝統行事です。
元日はもちろん、三が日(1月1日~3日)や松の内(一般的に1月7日まで)を含む期間を指すことが多いです。
古くから日本では、この時期に「年神様(としがみさま)」という豊作や健康を司る神様を家庭に迎える風習があり、門松やしめ縄、鏡もちなどの正月飾りを用意します。
家族や親せきが集まり、おせち料理を食べたり、年賀状を送りあったりすることで、新しい年を祝い合う行事です。
お正月の由来
お正月の起源は、古代の日本にさかのぼります。
稲作文化が根づいた日本では、年のはじめにその年の豊作と家族の健康を祈る儀式が行われてきました。
その中心にいたのが「年神様」。家々にやってくる年神様を迎えるために、門松やしめ縄を飾り、鏡もちをお供えするようになったといわれています。
また、平安時代にはすでに宮中で元日を祝う儀式が行われており、江戸時代には庶民にも広がっていきました。
こうした神事や慣習が、現代のお正月行事に受け継がれています(※諸説あり)。
| 呼び方 | 期間 |
| 元日(がんじつ) | 1月1日のこと(元旦は元日の朝) |
| 三が日(さんがにち) | 1月1日から3日までのこと |
| 松の内(まつのうち) | 1月1日から7日までのこと |
| 小正月(しょうしょうがつ) | 1月1日から15日(地域によっては20日)までのこと |

子どもへのわかりやすい説明
2歳児向け
●概要の伝え方
「おしょうがつは、あたらしいとしが はじまる おいわいだよ。みんなで“あけましておめでとう”ってごあいさつして、おせちっていう ごちそうも たべるんだよ。」
●由来の伝え方
「おうちには かみさまが くるっていわれていて、まつのはっぱを かざったり、おもちを おそなえするんだよ。」
3歳児向け
●概要の伝え方
「おしょうがつは、いちねんのはじまりを おいわいする たいせつなとき。みんなで おいしいものをたべたり、ねんがじょうをおくったりするよ。」
●由来の伝え方
「むかしのひとは、“としがみさま”っていう かみさまを おむかえして、いちねん げんきにすごせるように おいのりしていたんだって。」
4歳児向け
●概要の伝え方
「おしょうがつは、しんねんをむかえて、かぞくやともだちと いっしょに おいわいするひだよ。おせちや おとしだま、おまいりなど、いろんな しゅうかんがあるんだ。」
●由来の伝え方
「にほんでは むかしから、“としがみさま”という かみさまを おむかえするために かどまつや かがみもちを かざったり、たべものをそなえたりして、かみさまに「よろしくね」とごあいさつしていたんだよ。」
5歳児向け
●概要の伝え方
「おしょうがつは、いちねんのはじまりを おいわいする にほんのでんとうぎょうじ。おせちりょうりをたべたり、たこあげや かるたであそんだりして、たのしくすごすよ。」
●由来の伝え方
「むかしのひとたちは、“としがみさま”っていう そのとしのしあわせやけんこうを くれるかみさまを むかえるために、おうちに まつや しめなわをかざって、かがみもちをそなえていたんだ。そうして、みんなで いいとしに なりますようにって ねがっていたんだよ。」

関連情報
お正月には、たくさんの伝統的な遊びや風習があります。
たとえば「かるた」「こままわし」「はねつき」「たこあげ」など、日本ならではの正月遊びは、子どもたちにとっても貴重な体験になります。
また、書き初めや福笑いなど、五感を使った遊びも集中力や創造力を育むうえでおすすめです。
園では「年賀状づくり」や「おせちのぬりえ」など、子どもたちが正月行事に親しめる制作活動も効果的。日常から少し離れた特別な行事だからこそ、伝統文化への理解を深めるチャンスです。
お正月にちなんだ保育活動
お正月の文化や伝統を子どもたちが楽しく感じられるような活動例を紹介します。
導入しやすい室内遊びや製作活動を中心に構成しています。
- たこ作り&たこあげ
ビニール袋や紙袋で手作りのたこを作り、園庭でたこあげを楽しむ。風が弱い日でも遊べるよう工夫すると良い。
- 門松づくり(簡易版)
トイレットペーパーの芯や色画用紙を使い、小さな門松を製作。伝統行事に親しむきっかけに。
- 鏡もち製作
紙皿や紙粘土で鏡もち風の飾りを作成。三方や橙などの意味も一緒に伝えると理解が深まる。
- お正月ぬりえ/福笑い
獅子舞、だるま、羽子板などのぬりえや、福笑い遊びで日本の伝統的な遊びを体験できる。
- かるた大会
園オリジナルの「ひらがなかるた」や季節の言葉を用いたかるた遊び。グループ対抗戦にすることで盛り上がる。
- 干支にちなんだ動物遊び
その年の干支をテーマにしたごっこ遊びや製作。干支の動物について話を広げる導入にも。
- 年賀状制作(はんこ・お絵かき)
指スタンプや絵でオリジナルの年賀状づくり。お世話になった人への感謝の気持ちを込めることも伝えられる。
その他 お正月にまつわる様々な由来
お正月には子どもたちが知っているものがたくさんあります。由来や意味を知っておくと散歩先などで見かけたとき、スムーズに説明ができますよ。ぜひ一通り目を通しておきましょう。
【おせち】
おせちは、お節句(せっく)に神様にお供えした食べものが由来になっています。おせち料理にある食べ物にはそれぞれおめでたい由来があるのです。
| おせち料理 | 意味など |
| かまぼこ | 紅(あか)色は「めでたさ」白色は「神聖」を表します。紅白は縁起がよい色です。 |
| だてまき(伊達巻) | 伊達者(だてもの・おしゃれな男の人)の着物を表します。 |
| 栗きんとん | 金色に輝く宝物を表しています。栗は「勝ち栗」といって演技が良い食べ物 |
| 黒豆 | 「まめ」は健康を意味します。健康への願いが込められています。 |
【お年玉】
昔は年神さまにお供えしたお餅を配っていたことが由来になっています。もともとは新年をお祝いするためにもらっていたのがお年玉です。今ではお餅ではなくお小遣いになり、子どもにあげる風習に代わっていきました。
【門松】
年神さまが家にきたときに、松の木に宿るとされていたことが由来になっています。門松を飾っている期間イコール年神さまが家にいらっしゃる期間になるので、松の内(1月1日〜1月7日)の間は門松を飾っておくことが多いです。
【年賀状】
昔日本では、親戚やお世話になった人のお宅に新年のあいさつにいく風習がありました。しかし遠くの人にはなかなか伺えないので、書面で年始の挨拶をするようになったのがはじまりとされています。
まとめ
お正月は、日本の伝統や文化を子どもたちに伝える絶好の機会です。
ただお祝いするだけでなく、「なぜそうするのか」「どんな思いが込められているのか」を、年齢にあわせて伝えることで、行事の意味がぐっと深まります。
園での活動や家庭での関わりを通して、子どもたちが楽しく「日本の文化」に親しめるよう、この記事が少しでもお役に立てば幸いです。