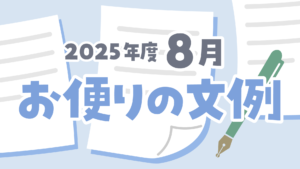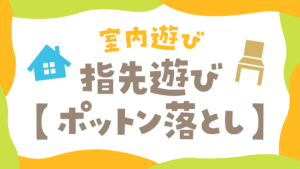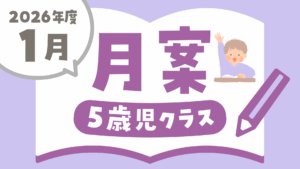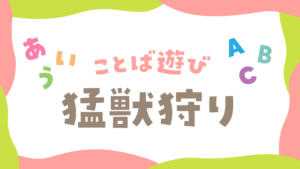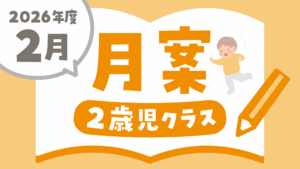保育園では昼食後に「お昼寝」が設定されていますが、元気いっぱいの子どもたちをスムーズに寝かしつけるのは簡単ではありません。
今回は、子どもの寝かしつけのポイントや、どのような環境が寝かしつけに適しているのかを分かりやすく解説していきます。
1.子どもを寝かしつけるときのポイント
子どもの寝かしつけは、保育者だけでなく保護者も「どのようにしたら寝てくれるだろう?」と頭を悩ませていることが多いです。
元気いっぱい遊んで楽しんだあとでも、スムーズに眠れる方法を試してみましょう。
1-1.事前に子供の入眠の癖を知っておく
一番大切なのは「子どもの入眠の癖」を知っておくことです。
子ども一人一人、入眠の仕方が家庭によって異なり、どのような体勢で寝るのが好きかなどを事前に入園前に聞いておくと良いでしょう。
手を繋ぎながら寝る子や、頭を撫でて欲しい子など、なるべく家庭での寝かしつけと同じような行動をすることで安心して寝付くことができますよ。
1-2.お昼寝前は静かに遊ぶ
寝かしつけはお布団に入る前から始まっていると考えましょう。
基本的に保育園では昼食後にお昼寝といった流れなので、昼食後の遊びは静かに遊べるような「お絵かき」や「絵本」などの動きが激しくないものを設定します。
寝るまえに体を動かす遊びをしてしまうと、体が興奮状態になりお布団に入ってもなかなか寝ることができなくなってしまいます。
1-3.安心できる触れ合いをしながら寝かしつける
寝かしつけの定番である「背中をトントンする」「手や足を優しくにぎにぎする」「おでこをくるくる撫でる」などは、一種のボディタッチであり、子どもが安心できる触れ合いとも言えます。
安心した気持ちになると、子どももスッと入眠できるので子どもに合った方法を試してみましょう。

2.寝かしつけに適した環境は?
寝かしつけ方法の他にも気をつけなくてはいけないのが「寝かしつける場所の環境」です。
どんなに寝かしつけ方法が良くても環境が悪いとぐっすり眠ることができないので、子どもたちが気持ち良く眠れる環境を整えましょう。
2-1.薄暗く、なるべく静かな環境を作る
入眠する際には、室内のカーテンを閉めて薄暗くすると眠りやすくなります。
真っ暗にすると、子どもたちの体勢や睡眠状況がわかりにくくなるので、少し明かりが漏れる程度が良いでしょう。また、ざわざわとうるさい中では寝つきも悪くなります。なるべく静かな環境を作りましょう。
完全な無音だと怖いと感じる子もいるので、寝かしつけ用のオルゴール曲やホワイトノイズをかけたり、保育士が子守唄を歌ってあげると安心できるはずですよ。
2-2.おもちゃなどの興味を引くものを近くに置かない
お昼寝をする部屋には子どもの興味を引くおもちゃ類を近くに置かないようにしましょう。
子どもがお布団に入っても近くにおもちゃがあると、遊びたい気持ちになってしまいます。
眠る気持ちになるためにも、おもちゃは近くに置かず子どもから見えない場所に移動しておいて下さいね。
2-3.室温、湿度に気をつける
天気によって保育室内の室温や湿度が変わってくるので、寝かしつけ前の適温チェックを行いましょう。
大人でも暑すぎたり寒すぎたりすると、なかなか寝つくことができませんよね。
また、湿度が高くじめじめしていると蒸し暑さを感じることもあります。
子どもがスッと寝れるような環境かチェックする癖をつけましょう。

3.子どもたちが寝ない原因は?
寝かしつけをしていても「今日はなかなか寝ないなぁ」と悩んでしまう時もありますよね。子どもが寝ないのには寝かしつけ方法や環境以外の何か原因があるかもしれません。
3-1.起床時間が遅い
保育園のお昼寝は大体12時前後から始まるところが多いですが、起床時間の遅い子は「まだ眠くない!」ということもあります。
連絡ノートなどに起床時間が書かれている場合は、遅く起きていないか確認してみましょう。
3-2.体力が余っている
雨の日など室内で過ごした日にありがちですが、午前中のうちに体力が発散できず子どもたちが疲れていないという場合もあります。
外遊びをすると自然に体をたくさん使って疲れて眠れるのに、室内遊びだと中々寝つくのに時間がかかることがあります。
室内での遊びを工夫したり、身体を動かすゲームを設定すると、良い運動になり寝かしつけしやすくなるでしょう。
3-3.体調が悪い
体調が悪く、なかなか寝つけない場合もあるので「普段の様子と違うかも?」と感じたら検温をしてみてください。子どもは急に体調を崩すので、何か変だなと感じたら様子を見ましょう。
体調が悪くなる前触れの可能性もあるので、すぐに眠れなくても近くに保育士がいるようにすると子どもも安心できますよ。

4.お家でできる入眠環境の作り方
上記に挙げた項目を意識しながら、家でもできる睡眠環境の作り方をご紹介します。
4-1.ルーティンを決める
スムーズに入眠するためには毎日のルーティンが重要です。
例えば、晩御飯→お風呂→歯磨き→絵本→布団 のように、布団に入るまでの生活の順番を家庭のリズムに合わせて決め、なるべく毎日同じ順番で過ごせるように意識しましょう。
続けていくうちに、身体が「絵本を読んだら寝る」と覚え、自然と眠れる体勢をつくりやすくなります。
4-2.時間を決める
上記で決めたルーティンの活動時間を決めましょう。
余裕がない場合は、最後の「絵本」の時間だけでも決めておくとリズムが整いやすくなりますよ。
(例)
18:30 晩ご飯
19:30 お風呂
20:00歯磨き
20:15絵本
20:30 布団
4-3.環境を整える
子どもは大人よりも体温が高いので、室温や湿度の設定に気をつけましょう。
【冬】
一般的に冬の子どもの寝室は室温が20℃〜23℃くらい、湿度が40%〜60%が快適だと言われています。20℃を下回る場合は暖房器具や加湿器を活用して寝室を適温まであげるようにしましょう。
【夏】
外気温より4℃〜5℃低く設定する温度が快適だとされています。たとえば外気温が31℃だった場合、エアコンの温度を26℃〜27℃に設定します。湿度は50%前後がいいと言われています。
まとめ 良好な保護者関係を築くために
子どもの寝かしつけのポイントや環境作りについてのお話をしてきました。
寝かしつけは苦労することがたくさんありますが、子どもの体力回復のためにも必要な時間です。
安心できる環境をしっかりと作ってから、子どもにあった寝かしつけ方法を実践してみましょう。
園での寝かしつけが大変な場合は何か原因があるのか考え、保護者の方にも「お家ではどうですか?」と聞いてみるのもおすすめです。子どもたちがゆっくりと気持ちよく寝れるよう試してみてくださいね!