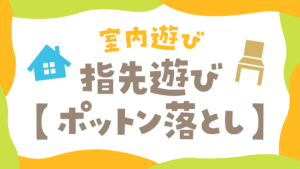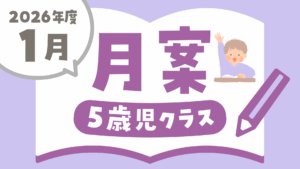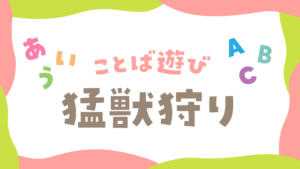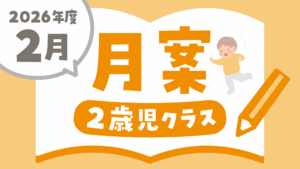このノートでは、『こどもが暴力をしてしまうとき』の背景や考え方、対応について書いています。こどもは気持ちのコントロールが苦手です。こどもが自分の気持ちに圧倒されるとき、こどもはとても強い不安にかられることを理解することが重要です。
こどもが暴力をしてしまう時の様子
こどもは些細なことでイライラします。自分のもの他人のものの境界もあいまいなので、こども同士のトラブルもたえません。単に泣いたり、イライラしたりするだけならいいのですが、こどもの中には叩いたり噛みついたりする子もいます。
暴力をしてしまう子も落ち着いていればとても人懐っこく可愛らしいところがあります。また、単に手を出してしまうのなら、大人も関わりやすいのではないでしょうか。
しかし一度暴力のスイッチがはいってしまうと、豹変したかのように攻撃してしまうこどももいます。そのような子にたいして、どう関わるべきか悩むことはないでしょうか。
どうしてそうなるのか

これまでのノートにも書いてきたように、こどもは自分の不満を抱えるのがまだまだ苦手で、イライラしやすい存在です。大人のイライラは問題がはっきりしていることが多く、具体的にイライラを処理することができます。
一方のこどもは、イライラしてもいったい何が自分をイライラさせているのかわからなかったり、どうしたら解決できるか考えることができないことが多くなります。
そうなると、とにかく目の前の気にくわない存在を、こらしめてやろう!消してしまおう!という考えにいたります。それは当然のことですよね。
その結果、叩いたり、噛みついたりしてしまいます。少し年齢があがってくれば、落ち着いて状況を整理し、意見を主張するなど双方向のやりとりが可能になります。
しかし、そもそも不安や不満をなんとかできた経験が少ないと、いつまでも乱暴なやり方にこだわらなければなりません。乱暴なやり方に見える問題解決の手段は、こどもにとってもわけのわからない取りあえずの手段です。
自分でコントロールできたわけではないので、問題が解決できるという自信も身に付けられません。そのため、私たちの目から見て、暴力に頼ってしまいがちなこどもは、自尊心が低いことも考えられます。
対応方法(考え方)
暴力はしてはいけません。こどもがするなら、止める必要があります。叱るべきか否かは、保育園の場合は年齢によって異なるかと思います。幼稚園の年齢であれば、少なくともいけないことであると伝える必要があると思います。
こどもの行動が激しかったり、危険であったりすると、大人も感情的になりやすくなります。こどもの行動をとめる刹那は、短くはっきりと『雷を落とすと昔からいうように』力をこめて伝えます。
しかし、こどもが行動を止められたのであれば、それ以上の追撃は必要ありません。ゆっくりと大人も落ち着きます。
こどもが行動を止められたなら、暴力をしそうになったことを責めるのではなく、止められたことを称賛する方が重要です。
こどもの行動が止まらない、あるいは暴力をしてしまったというのであれば、しっかりとこどもを止めてあげないといけません。こどもは自分の行動が制止されて嫌がりますが、『不満や不安を抱えているこどもは、孤独です。』
身体をとめてあげることで、自分自身は守られていて不満や不安を必要以上に感じなくていいことを体験することができます。もちろんこのとき、大人が感情的になっているとこどもは、恐怖心を募らせます。そしてこどもは必ずどこかで落ち着きます。無限の体力ではないので、それは『大人の力を借りてこどもが落ち着いた』ということです。
暴力をうけたのがこどもの場合、当然、暴力をうけたこどもの安全が第一です。しかし、暴力をしたくなる不安や不満を大人が抱えられるという態度がないと、いつまでもこどもは、イライラしたときどうしたらいいかわかりません。日頃から、こどもの気持ちのコントロールに寄り添えているかが重要です。
こちらも参考にしてください。