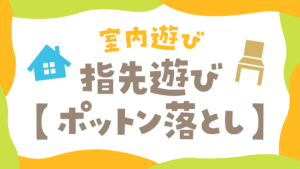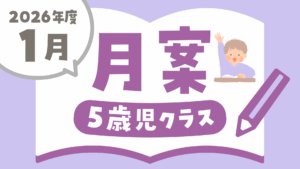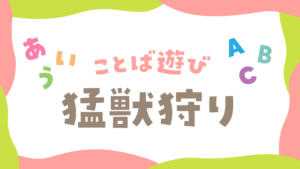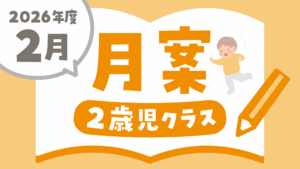5月5日は「子どもの日」。こいのぼりを飾ったり、柏餅を食べたりと、春の訪れとともに子どもたちの健やかな成長を願う大切な行事です。
本記事では、子どもの日の意味や由来、年齢別の説明方法、保育現場で実践できる活動例まで、保育者・保護者に役立つ情報をわかりやすくご紹介します。
1.子どもの日とは
子どもの日は、5月5日に行われる国民の祝日で、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する日」として1948年に制定されました。男の子の成長を願う「端午の節句」とも関係が深く、現在ではすべての子どもの健康と幸せを願う日として広く親しまれています。
この日は、こいのぼりを飾ったり、五月人形を飾ったり、菖蒲湯に入るなど、昔ながらの風習も多く残っています。
2.子どもの日の由来
子どもの日は、もともとは「端午の節句」と呼ばれる五節句のひとつで、中国から伝わった風習に由来しています。旧暦の5月は病気が流行しやすい時期とされており、邪気を払うために菖蒲を使った行事が行われてきました。
鎌倉時代以降、菖蒲(しょうぶ)が「尚武(しょうぶ=武をたっとぶ)」という言葉と結びつき、男の子の健やかな成長と出世を願う節句として定着しました。昭和になってからは、男女を問わず、すべての子どもをお祝いする「子どもの日」として、国民の祝日に制定されました。

3.子どもへのわかりやすい説明
2歳児向けの説明
「きょうは“こどものひ”だよ。こいのぼりが、おそらをおよいでるね。みんながげんきにおおきくなれるように、おいのりするひなんだよ。」
3歳児向けの説明
「こどものひは、みんながすくすくそだつようにおいのりするひだよ。こいのぼりや、よろいやかぶとをかざって、つよくてげんきなからだになりますようにってねがうんだよ。」
4歳児向けの説明
「こどものひは、こどもたちのけんこうとしあわせをねがうひなんだよ。むかしは“たんごのせっく”といって、男の子がげんきにおおきくなるように、かぶとやこいのぼりをかざっておいわいしていたんだって。いまでは、すべてのこどもたちのおまつりになったんだよ。」
5歳児向けの説明
「こどものひは、みんながげんきにそだって、たのしくくらせるようにおいのりするひなんだよ。」
「むかしのにほんでは、5がつにびょうきがはやったから、“しょうぶ”というはっぱをつかって、わるいものをおいはらっていたんだって。」
「それが“たんごのせっく”というぎょうじになって、よろい・かぶとをかざったり、こいのぼりをあげたりして、おいわいするようになったの。いまでは、すべてのこどもたちのおまつりになったんだよ。」
4.関連情報
子どもの日は、保育の現場でも子どもたちが日本の伝統文化に触れる良い機会です。こいのぼりやかぶと、柏餅、菖蒲湯などの風習は、保育者の声かけや絵本を通じて楽しみながら伝えることができます。
また、「母に感謝する日」という側面もあるため、保護者への感謝の気持ちを込めた制作やメッセージカードづくりもおすすめです。5月の導入保育としても、自然と文化をつなぐ題材として非常に活用しやすいテーマです。
5.子どもの日にちなんだ保育活動
以下のような活動は、年齢や発達に応じてアレンジ可能です。
- こいのぼり制作(指スタンプ、切り紙、にじみ絵など)
- かぶとづくり(新聞紙や画用紙で折ってかぶる)
- 柏餅・ちまきの絵本や紙芝居の読み聞かせ
- 室内での「こいのぼりくぐり」ゲーム
- 菖蒲湯ごっこ(菖蒲の葉に触れる・匂いを嗅ぐ体験)
- 保護者への「ありがとうカード」制作
- 日本の伝統行事に関するクイズあそび

まとめ
子どもの日は、こいのぼりや五月人形といった華やかな風習とともに、子どもたちの健やかな成長を願う大切な行事です。
由来や意味を年齢に合わせてやさしく伝えながら、文化に親しむ時間として保育に取り入れることで、子どもたちの心に残る1日となるでしょう。
日々子どもたちを支えている保育者や保護者にとっても、「育ちを喜ぶ日」として、あらためて子どもたちの存在の大切さを感じる機会になりますように。