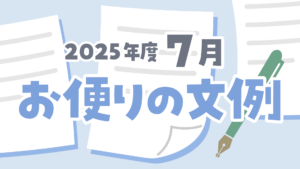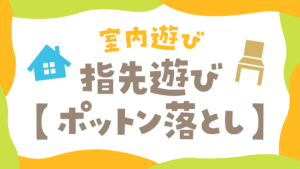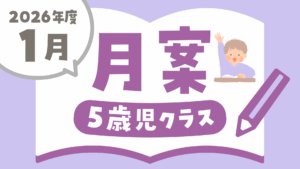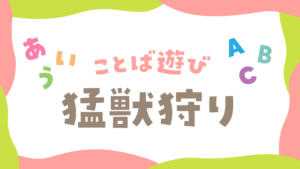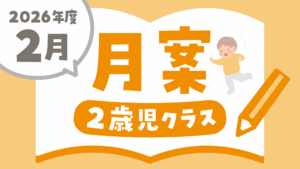保育園では子どもたちが元気いっぱいに遊び、学ぶ中で、思わぬ怪我をしてしまうこともあります。
安全で安心できる保育環境を整えるためには、日々の環境構成が大きな鍵となります。
この記事では、保育園での怪我の実態や、怪我を未然に防ぐための環境づくりのポイントについて詳しく解説します。
1.保育園における1年間の怪我の数
厚生労働省の「保育所における事故報告集計」によると、全国の保育施設で年間に報告されている事故は数千件にのぼります。
たとえば、2023年度には全国の認可保育園から約7,000件以上の事故報告が寄せられました。この中には転倒や衝突、誤飲、熱傷など、様々な種類の怪我が含まれています。
年齢別で見ると、特に動きが活発になってくる1~2歳児の事故件数が多い傾向にあります。体の発達とともに行動範囲が広がる一方で、危険の予測や回避がまだ難しい年齢だからです。

2.怪我をしやすい環境とは?
怪我をしやすい環境にはいくつかの特徴があります。
- 視界が悪い配置(職員の死角が多い)
- 滑りやすい床材や段差
- 年齢に合っていない遊具や備品
- 物が散乱している保育室
- 活動内容に対して空間が狭すぎる 等
また、季節や時間帯によってもリスクは変化します。
たとえば、雨の日には床が濡れて滑りやすくなり、夏場は熱中症による転倒リスクも高まります。
日々の状況に応じた環境の見直しが必要です。

3.怪我を防ぐ環境構成のポイント
3-1.起床時間が遅い
家具や棚の配置を工夫し、保育者の視界が遮られないようにします。
子どもの動きを常に把握できることで、危険な行動への素早い対応が可能になります。
3-2.年齢や発達に合った遊具選び
月齢や発達段階に応じた遊具・玩具を選ぶことが大切です。
幼い子に対しては、角の丸い素材や高さの低い遊具を選びましょう。
3-3.転倒・衝突の予防
床には滑りにくい素材を使用し、クッションマットなどの安全対策も検討します。
また、家具の角にはコーナーガードをつけておくと安心です。
3-4.定期的な環境チェック
日々の点検と月1回以上の環境見直しを行い、「危険の芽」を早期に発見・除去しましょう。
職員全体で共有できるチェックリストの導入も有効です。
3-5.子どもと一緒に“安全”を学ぶ
保育者だけでなく、子どもたちにも「危ないこと」や「どうやって気をつけるか」を伝えることで、主体的な安全意識を育てていきます。

4.もし怪我をしてしまったら?
どれだけ注意していても、怪我をゼロにするのは難しいものです。大切なのは、迅速で適切な対応です。
- まずは応急処置(止血・冷やす・安静など)
- 保護者への連絡(怪我の様子、対応内容、今後の見通しなどを丁寧に)
- 事故報告書の記入と振り返り
- 職員間での情報共有と再発防止策の検討
子どもが安心できるよう、気持ちに寄り添った対応も重要です。
また、同じ状況が繰り返されないよう、環境や保育方法の見直しを徹底しましょう。

5.ヒヤリハットを記録しよう
「ヒヤリハット」とは、重大な事故には至らなかったものの、“ヒヤリ”としたり“ハッ”とした出来事のことを指します。
ヒヤリハットの例
- 子どもが机の角にぶつかりそうになった
- 遊具から落ちかけたが、すぐに保育者が気づいて支えた
- おもちゃの部品を口に入れそうになった 等
一見すると「大丈夫だったから問題ない」と思いがちですが、ヒヤリハットは重大事故の前兆であることが多く、適切に記録・共有することで事故の再発防止に大きくつながります。
まとめ
保育園での怪我は完全に防ぐことはできませんが、日々の環境構成と職員の意識によって、大きな事故のリスクは大きく減らすことができます。
子どもたちがのびのびと過ごしながらも安全に生活できるよう、安全で安心できる園づくりのために、まずは今日の保育環境を見直してみましょう!