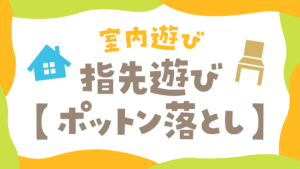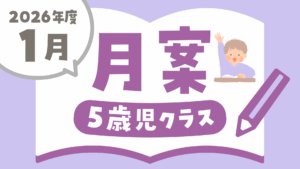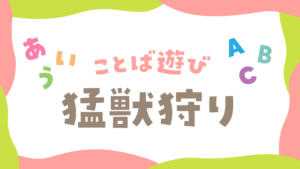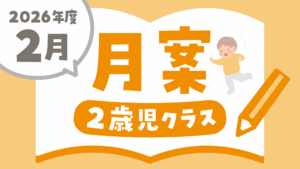一年の終わりを迎える「大晦日」は、日本の伝統文化や生活の節目を実感できる特別な一日です。
年越しそばを食べたり、除夜の鐘を聞いたりと、家庭ごとにさまざまな過ごし方があります。
この記事では、大晦日の意味や由来を丁寧に解説し、保育現場で子どもたちに伝える方法や、保育に取り入れられる活動例をご紹介します。
「大晦日」とは
大晦日とは、1年の最後の日である12月31日のことを指します。
「晦日(みそか)」はもともと毎月の最終日を意味しますが、特に12月の晦日を「大晦日」と呼び、年末の特別な日として親しまれています。
この日は、1年の締めくくりとして、家族で年越しそばを食べたり、大掃除をしたり、除夜の鐘を聞いたりといった風習があります。
また、新しい年を気持ちよく迎えるために、自分自身を見つめ直す日としての意味合いもあります。
大晦日の由来
大晦日の風習は、古くは奈良時代から平安時代にかけて行われていた「年越しの祓(はらえ)」や「年籠り(としごもり)」に由来するといわれています。
年越しの祓では、一年の罪や穢れを清める儀式が行われました。また、年神様を迎えるにあたり、家長や村の代表者が神社や家にこもり、無事を祈願する「年籠り」も重要な習わしでした。
こうした風習が現代の「大掃除」や「年越しそば」「除夜の鐘」に形を変えて残っています。

子どもへのわかりやすい説明
2歳児への説明
「おおみそかっていうのは、いちねんのいちばんさいごのひなんだよ。
みんなでおへやをきれいにしたり、おそばをたべたりするんだ。あしたはあたらしいねんがくるよ!」
3歳児への説明
「おおみそかは、いちねんがもうすぐおわるひ。
おうちのひととおそばをたべたり、おおそうじをしたりするんだ。
よるには、おおきなおてらからゴーンっておとがなるんだよ。」
4歳児への説明
「おおみそかは、としがかわるまえのたいせつなひ。
『ことしもありがとう』っていって、おへやをきれいにして、そばをたべて、じぶんのきもちもすっきりするんだ。よるに『じょやのかね』っていうかねのおとがなるんだよ。」
5歳児への説明
「おおみそかは、いちねんをふりかえって、あしたからはじまる『あたらしいいちねん』をきれいなきもちでむかえるひ。
そばをたべるのは、『ながいきしますように』っていういみもあるんだよ。
108かいなるじょやのかねは、人のわるいきもちをとりのぞくためのかねなんだって。」
読書週間に関連する情報
大晦日は、日本人にとって“区切り”や“感謝”の意味を持つ大切な日です。
保育園では年内最終登園日が大晦日より前のことが多いため、少し早めに「一年のしめくくり」として行事を取り入れるのがおすすめです。
また、家庭との連携を意識し「大掃除の手伝い」「年越しの習慣」など、保護者と一緒に経験してもらえる機会を促すのも有効です。
子どもたちと1年を振り返りながら、「ありがとう」を伝える機会としても活用しましょう。

読書週間にちなんだ保育活動
- 「ことしのありがとうカード」製作(自分や友だち、先生への感謝を書く)
- 「おそうじあそび」ごっこ(雑巾や布で室内を楽しく掃除)
- カレンダー作り(来年の目標や干支の動物を描く)
- 年越しそば製作(紙や毛糸でそばを作って遊ぶ)
- 除夜の鐘を聞く活動(動画などで鐘の音を体験)
- 一年の思い出発表会(グループで1年の楽しかったことを共有)
- お正月との違いを知る紙芝居や絵本の読み聞かせ
まとめ
大晦日は、一年を締めくくる大切な節目。保育の中でも、子どもたちに「感謝」「ふりかえり」「新しい年への期待」を伝えるよい機会です。
日々の保育の中に、大晦日の意味を自然に取り入れ、子どもたちが“今年もがんばったね”“また来年も楽しく過ごそうね”という気持ちで年を越せるようにサポートしていきましょう。
保育者の関わり方次第で、年末の行事も子どもたちの心に残る素敵な体験になります。