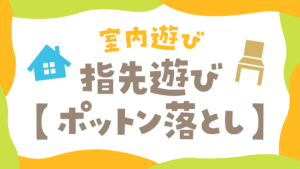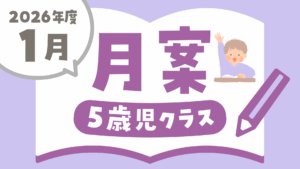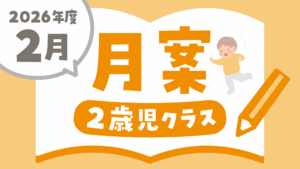毎日の保護者対応、新人保育士にとったら緊張する時間かもしれません。何を話せばいいのか、どのように伝えたらいいのか悩むことも少なくないはず。
一方保護者にとったら、仕事が終わり、やっと我が子に会える大事な時間。「楽しく過ごせていたかな」「ご飯はたくさん食べれたかな」と考えながらお迎えに来られる保護者が多いでしょう。
そんなお迎え時こそ保育士は、保護者一人ひとりと向き合える時間にしていきたいですね。
今回は、お迎え時の会話の仕方やポイントについてまとめました。
1.保護者対応で何を話す?
送迎のタイミングというわずかな時間ですが、この時間にしっかりとコミュニケーションを取ることが大切です。
とはいえ何を話せばいいのか、うまく伝えるにはどうしたらよいのかなど、初めはわからないことばかりだと思います。
そんな時は次の3つを軸に話すことを心がけてみてください。
1-1.園での子どもの様子
まずは園での1日のその子の様子を端的に伝えましょう。
園の方針にもよりますが、特に変わったことがない日は「元気でしたよ〜」「変わりなく楽しく過ごしていましたよ」など一言で終わることもあるかと思います。
離れている間、自分の子がどのように過ごしていたのかを知りたい保護者の気持ちに寄り添うためにも、とくに変わりがない日でも「具体的な一言」を追加してはなしてみましょう。
例えば…
・友達との関わり
「今日も仲良しの○○くんと一緒に大好きなプラレールで遊んでいましたよ」
「0歳児クラスの小さい子のお世話をしてくれてとても助かりました」
・食事量
「苦手な野菜も一生懸命食べていましたよ」
「今日のスープは好みだったようでおかわりして食べました」
・遊び
「ぬりえ遊びが楽しかったみたいで、またやりたいと言っていました」
「早く外で遊びたいと言って1番に帽子をかぶって待っていました」
など、細かい内容は連絡帳に記載しているため、限られた時間で端的にその子のエピソードや様子を伝えられると良いですね。
1-2.お知らせや伝達事項
衣替えのお願いや荷物の不備、行事の連絡などを保護者に伝える場合は、分かった時点で早めに伝えるようにしましょう。また、「お願い」なのか「相談」なのかを明確にし、曖昧な伝達にならないことが重要です。
例えば、多くの園では子どもの持ち物には名前の記入をお願いしていますよね。もし名前の記入がなかったり、字が消えて読めなくなっている場合はすぐに保護者に伝え、記入してもらうようにお願いします。
そして、トレイトレーニングの開始時期やトレパンの準備などは保護者に「相談」をし、園が主導で勝手に決めたり先々と進めてしまうことのないようにしましょう。
家庭それぞれに方針があり、状況や環境が違うため、伝達事項一つにしても保護者への伝わり方に注意が必要です。
1-3.保護者の悩みや相談事にのる
保護者対応をしてると、最近疲れていそうだな、少し余裕がないなと感じる保護者も中にはいるかもしれません。
日々コミュニケーションをとっている保育士だからこそ、保護者の変化にも気づくことができます。
そんな時は優しく「お仕事お疲れ様です。あまり頑張りすぎないでくださいね。もしなにか悩み事などがあればいつでも相談してください」などと声をかけ、保護者の悩みや不安に寄り添って話を聞き、話しやすい関係性を築きましょう。
また、無理に聞き出すのではなく保護者が相談したいと思える保育士でいることが重要です。そのためにも日々の保護者対応で真摯に関わることを意識しましょう。

2.保護者対応で意識すること
ここからは、保護者対応での会話をよりよく充実させるために意識すべきポイントを解説していきます。
2-1.適切な言葉選び
適切な言葉を使って話すことは信頼関係に直結します。1日のうちの、保護者と関わるわずかな時間のなかで、不適切な発言や間違った言葉遣いをしてしまうとあまりいい印象ではありませんね。
少し打ち解けた保護者などには、つい若者言葉や友達言葉を使ってしまいそうになるかもしれませんが、社会人としてどんな状況であっても丁寧な言葉遣いを心がけていくことが大切です。
2-2.傾聴と共感
保護時対応では、つい保育士が話すばかりになりがちですが、実は保護者の話しを聞くことの方が大切です。
園での子どもの様子をもちろん保護者は知りたいですが、それ以上に自分の悩みや考えを聞いて欲しいと思っているかもしれません。
そして、保護者の話を聞く時は、「たしかにそうですよね」「大変でしたね」などと共感を示しましょう。
ただ相槌を打つのではなく、保護時の気持ちに寄り添った「傾聴」と「共感」を意識してみてください。
保護者対応では、保護者の話しを中心に展開できると良いですね。
2-3.ネガティブな報告で終わらない
「今日は野菜が食べれず残しました」「トイレが間に合わず、おしっこが漏れてしまいました」など、必要な報告ではあるものの、実際に保護者が聞くと少しショックな気持ちになる伝達事項も中にはあります。
この場合、話の最後には必ず今日一日でその子が頑張ったことや成長したことなどのエピソードを伝えて締めくくるようにしましょう。
そうすることで、マイナスな内容の伝達事項も余裕を持って受け止めやすくなります。
2-4.すぐに答えられない時は主任や園長に相談する
保護者対応をしていると、園に対しての様々な要望や質問、相談などを保護者から聞くことがあります。
答えられるものは自信を持って答えるようにしましょう。ただ、わからないことや自信がないことは素直に
「園長に確認しますね」
「すみません、わからないので明日改めてお伝えさせてください」
と伝え、曖昧な返答や間違ったことを伝えないように気をつけましょう。
わからないことを素直に謝れる事は、保護者にとって信頼できる保育士です。勇気を出して伝えましょう。

3.【事例別】保護者への伝え方例文
ここからは、私が実際に保護者対応においてやりとりした内容をもとに例文を作成しました。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
3-1.怪我をしたことを伝える場合
保育園では怪我が付きもの。しかし、子どもを預かっている以上怪我をしてしまった場合は謝罪が必要です。
まず謝罪をしてから状況や処置内容を伝えましょう。
【例】
「フリーの保育士と私の2人で見ていたのですが、○○くんが園庭遊びの時につまずいて転んでしまいました。目が行き届いておらず、怪我をさせてしまい申し訳ありませんでした。
少し右膝を擦りむいてしまったため消毒をして絆創膏を貼っています。今は気にしていないようですが、お風呂の時はしみて痛がるかもしれません。
念のためお家でも様子を見ていただけますか?もし何か気になることがあればすぐに教えてください。」
3-2.友達とのトラブルを伝える場合
友達との喧嘩やトラブルがあった際、怪我をしたり、させてしまうことがあります。その場合は必ず怪我をしてしまった子の保護者へトラブルの経緯と共に怪我の状態を伝える必要があります。
【例】
「○○くんが電車のおもちゃで遊んでいる際、友達と取り合いになってしまいました。友達がおもちゃを引っ張った勢いでそのまま○○くんの顔に当たり、頬に少しアザができています。
すぐに冷やして処置をしましたが、お家でも様子を見ていただき、もし何か変化があればすぐに教えてください。」
3-3.持ち物についてお願いをする場合
子どもの持ち物に名前が書かれていなかったり、ロッカーに用意されている衣服がサイズアウトしていることなどは保育園ではよくありますね。そんな時は保護者へ持ち物の確認や入れ替えをお願いしましょう。
【例】
「○○ちゃんのお洋服ですが、少しサイズが小さいようでお着替えをする時に脱ぎにくそうにしています。自分で着脱をしたいという意欲があり、その気持ちを尊重したいのでワンサイズ大きい服をご用意いただけますか?」
3-4.保護者の相談にのる場合
送迎時、保護者の様子がおかしいな、少し疲れているのかな?と感じた場合や保護者から直接相談事があった場合、保育士は保護者の気持ちに寄り添って話を聞き、必要なアドバイスや共感をするようにしましょう。
【例】
夜泣きが酷いと連絡帳に書かれていましたが、あまり寝れてなくて疲れていませんか?お仕事も毎日頑張られているから、もしお休みできるタイミングがあれば遠慮なく保育園に預けて休んでくださいね。またなにか困ってることや心配なことがあればいつでもご相談ください。」
4.保護者対応をする上で忘れてはいけないこと
あくまで保育園は、大切なお子様を預かる場所。保護者に対して上から目線で話したり、園の方針を押し付けることは決してしないように気をつけましょう。
保護者の立場を考え、適切な言葉選びを心がけることがポイントです。
丁寧でポジティブな言葉遣いを意識して保護者との良好な関係を築いていきましょう。

まとめ 良好な保護者関係を築くために
いかがでしたか?今回は保護者対応について事例をもとに解説しました。
人と人の関係を築いていくためにはマニュアルにこだわりすぎないことも大切です。
大切なのは相手の気持ちに寄り添うこと、真摯に向き合うこと。
毎日ひとつひとつ積み重ねていき、信頼関係を築くことが最大のポイントです。
保護者対応に悩んでいる人、苦手意識がある人はぜひ本記事を参考にして、保護者と良好な関係を築いてくださいね。