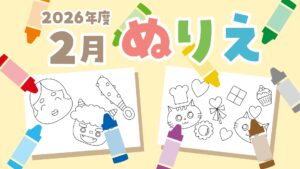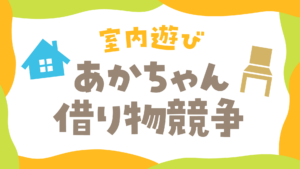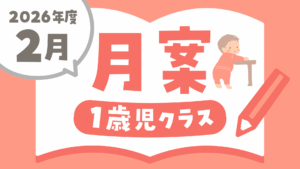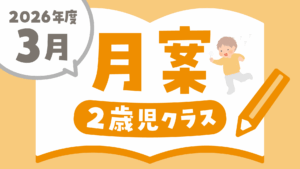一年のうちで昼が最も短く、夜が最も長くなる「冬至」。
ゆず湯やかぼちゃなど、季節を感じる風習があるこの日には、昔の人々の知恵や祈りが込められています。
保育の中でも、子どもたちが季節の移り変わりを感じ、健康や自然への感謝の気持ちを育む機会にぴったりの行事です。
今回は、冬至の意味や由来、子どもへの伝え方や保育での活用アイデアをご紹介します。
冬至とは
冬至(とうじ)は、毎年12月21日頃に訪れる「二十四節気」のひとつで、一年の中で最も昼の時間が短くなる日です。
太陽の高さが最も低くなることから、日照時間も短く、寒さが本格化する時期とされています。
日本ではこの日を「太陽の力が最も弱くなる日」として、昔から「運を上昇させる日」と考えられてきました。
無病息災を願って「ゆず湯に入る」「かぼちゃを食べる」などの風習が今でも続いており、季節の節目として大切にされています。
冬至の由来
冬至は、古代中国の「陰陽五行説」にもとづく思想から伝わったとされています。
「陰(夜)」が極まり、「陽(昼)」に転じる節目の日とされ、太陽の力が再び強まることから「一陽来復(いちようらいふく)」=運気が回復する日として縁起の良い日と考えられてきました。
日本ではこの思想と農耕文化が結びつき、「体を温めて健康を保つ」「病気を予防する」という意味合いから、ゆず湯やかぼちゃを用いた風習が広まりました。
地域によっては、小豆粥やこんにゃくを食べる習慣もあります。

子どもへのわかりやすい説明
2歳児への説明
2歳児には
「きょうは“ふゆのひるが いちばんみじかいひ”なんだよ」
と、言葉よりも体験中心で伝えるのがよいでしょう。
「おふろに ゆずが はいってるよ」「かぼちゃたべて げんきになろうね」
と、生活に寄り添った声かけで冬至を楽しむ雰囲気を伝えます。
由来は触れず、
「おいしいたべものをたべて、おふろでぽかぽかになるひ」
として季節感を味わえるようにします。
3歳児への説明
3歳児には
「ふゆのなかで、いちばん よるが ながいひが“とうじ”だよ」
と、日照時間の違いに触れながら説明すると良いでしょう。
「おそとが すぐまっくらになるね」「だから、おふろで からだをあたためるんだよ」
と結びつけます。
由来については
「むかしのひとは、“おひさまが ちょっとずつ つよくなるよ”ってよろこんでたんだって」
と話すと、自然への感謝を感じやすくなります。
4歳児への説明
4歳児には
「とうじは、ひるが いちばんみじかくて、よるが いちばん ながいひ」
と季節の変化をより具体的に説明できます。
「この日から、すこしずつ おひさまが ながくでてくるから、“あかるいきせつ”が もどってくる しるしなんだよ」
と伝え、
「だから、からだをあたためたり、げんきになるものを たべるんだね」
と風習の意味にも触れましょう。
かぼちゃ=ビタミンたっぷり、ゆず=いいにおいとぽかぽか、と感覚的にも伝えられます。
5歳児への説明
5歳児には、冬至の意味をより深く伝えられます。
「とうじっていうのは、ひが いちばん みじかくなるひで、“これから ひが のびていくよ”っていう しるしの日なんだよ」
と話すと、太陽との関係が理解しやすくなります。
由来についても
「むかしのひとは、たいようが よわくなるのを こわがってたんだって。だから、ゆずや かぼちゃをつかって、“びょうきを よせつけない”ようにしたんだよ」
と、自然や健康への願いがこめられた風習であることを伝えましょう。

関連情報
冬至は保育現場において、季節の変化を五感で感じたり、昔の人の知恵や習わしを伝えたりする良い機会です。
天気や気温、日照時間の変化を子どもと一緒に観察したり、「冬至=太陽が生まれ変わる日」として自然への感謝を伝えることで、命や季節の循環への気づきを育てることができます。
また、保護者に向けては、ゆず湯やかぼちゃ料理の紹介、家庭でできる冬の健康習慣を知らせる便りに活用しても良いでしょう。
地域によって風習が異なる場合もあるため、多様性に触れるきっかけとしても活用できます。
冬至にちなんだ保育活動
冬至をテーマにした活動は、季節を感じ、身体も心も温まる内容にするとよいでしょう。
- かぼちゃスタンプアート:かぼちゃの断面を使ってスタンプ遊び。五感を使った制作活動に。
- ゆずのにおいあそび・湯あそび:実際のゆずを触ったり、香りをかいだりして、嗅覚体験に。
- お風呂ごっこあそび:お部屋にたらいを置いて「ゆず湯ごっこ」。紙のゆずや温泉ごっこも◎
- 「ひがみじかい」観察遊び:昨日と今日で昼間の長さを比べる絵日記活動や時計あそびで感覚的に学習。
- 紙芝居や絵本の読み聞かせ:「ふゆのおひさま」「ゆずとおふろのおはなし」など。
こうした活動を通じて、冬ならではの行事と知恵を自然と子どもたちの記憶に残していきましょう。

まとめ
冬至は、季節の節目を感じながら、体をいたわる暮らしの知恵がつまった大切な日です。
保育の中では、子どもたちに「自然とともに生きる」という感覚や、昔ながらの風習の意味を楽しくやさしく伝えることができます。
ゆずやかぼちゃにふれる体験は、子どもにとって特別な冬の思い出になるはず。家庭や地域と連携しながら、冬至を“心あたたまる行事”として取り入れてみてはいかがでしょうか。