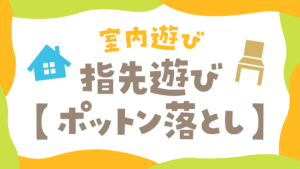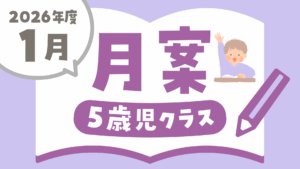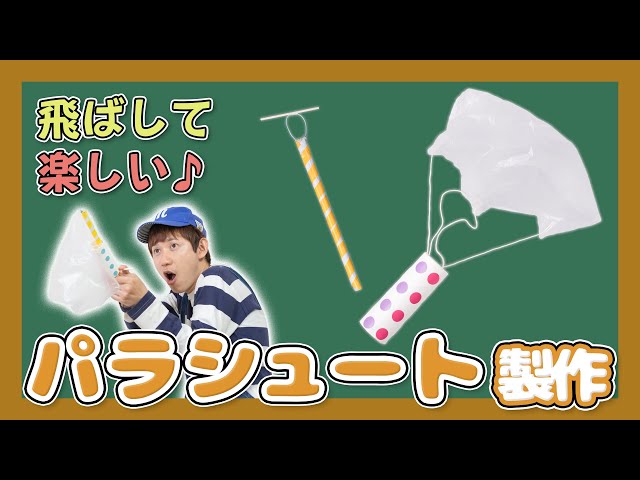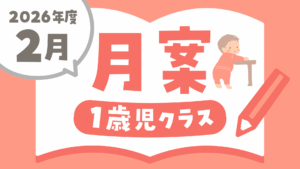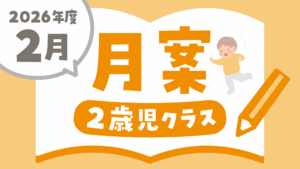「落ち着かない子」は怪我をしやすいので、安全に配慮しながら関わることが大切です。そのため、重要なのは職員や保護者との情報の共有や連携です。このノートでは、保育園や幼稚園で「落ち着かない子」について、その理由や対応について書いていきますので、少しでも日々の保育の参考になれば幸いです。
落ち着かない子の様子
みんなで歌を歌っているのに、ひとりだけ違うことをしている子はいませんか。
その子は、みんなで絵を描いているのに、すぐに席を立って歩いてしまうかもしれません。あなたが声をかけると、その場では元にもどりますが、長続きはしません。また別の興味関心に吸い寄せられて席を立ってしまいます。
この様な子は、真面目にとりくまずにふざけているようにも見えます。
なんでそうなるの?
とうぜん、不真面目なわけではなく、ふざけているわけでもありません。
この様な子は、『やりたい!という気持ちを抑えるのが苦手』です。目や耳に入る情報を取捨選択できず、感じたこと全部に反応しているかもしれません。
また、刺激に飢えているという可能性もあります。「いろんな刺激を感じたい!」という気持ちがあると、新しい刺激を求めて落ち着かなくなります。

対応方法(考え方)
普段から落ち着かないこどもの場合、彼らは刺激・情報に反応しやすいので、なるべく刺激の少ない環境が必要です。たとえば、掲示物をシンプルにする、席の位置を変える、パーテーションを使用するなどの工夫が考えられます。
ただ、環境の配慮にも限度がありますし、なんにも刺激のない環境がこどもの成長に良いともいえません。こどもが落ち着かなくても、怪我をしない程度に許容するおおらかさも必要です。園でできることは何かを保護者や職員間で話し合うことが大切です。
そもそも、こどもは成長のために新しい刺激を求めるものです。どうしても座っている必要がある場合、可能ならば様々な椅子があってこどもが選べると良いです。くるくる回れる椅子、ふかふかの椅子などなど、こどもの足りない刺激を与えられると、こどもが落ち着きやすくなります。
やりたいという気持ちが溢れることも大切ですが、それを持続させていくことも同じくらい重要です。こどものできたことをありのままに認め、達成感を共有する大人の姿勢が求められます。